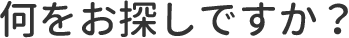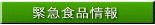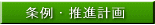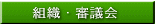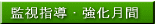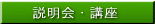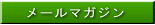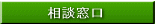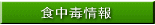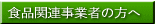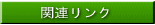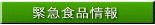
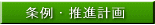
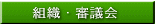
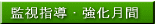
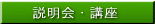
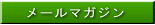
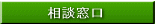
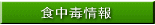

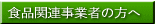

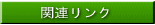
食中毒から身を守る3原則は、「清潔」・「迅速」・「温度管理」です。家庭や職場、学校などにおいてしっかりと予防対策をしましょう。
食中毒から身を守る3原則
|
清潔
|
菌を付けない!!
|
- 調理前、食事前、用便後には、手をよく洗いましょう。
- 鮮度の良いものを管理の良い店で購入しましょう。
- 台所は整理整頓し、常に清潔にしましょう。
- まな板、ふきん等は、十分に洗浄消毒をしましょう。
- 魚介類は、真水で十分洗い、専用まな板で調理しましょう。
- 包丁、まな板は、食材ごとに区分するのが最良です。共用する時は、別の食材に使用する前によく洗浄し、熱湯などで消毒しましょう。
- ハエ、ゴキブリ等の衛生害虫は、定期的に駆除しましょう。
|
|
迅速
|
菌を増やさない!!
|
- 調理は手際よくしましょう。
- 調理を中断する時は、食品を室温放置せず、冷蔵(冷凍)保存しましょう。
- 調理した食品は、早く食べましょう。
- 温かい料理は温かいうちに(65℃以上)、冷たい料理は冷たいまま(10℃以下)食べましょう。室温放置では、細菌が容易に増殖します。
- 食品を長時間放置しないようにしましょう。
|
|
温度管理
|
菌を増やさず、やっつける!!
|
- 加熱時は、中心部まで十分火を通しましょう。
- 生鮮食品や調理後の食品は10℃以下、刺身などは4℃以下、冷凍保存は-15℃以下で保存しましょう。
- 冷蔵庫は詰め込み過ぎないようにしましょう(最大7割まで)。
- 解凍する食材は、必要分を冷蔵庫内または流水解凍(容器を利用)しましょう。
- 残った食品は、清潔な容器に小分けして冷蔵(冷凍)保管し、再加熱するものは、十分加熱しましょう。
- 時間が経過しすぎたら、思い切って廃棄しましょう。
|
台所の衛生を考えよう!
|
まな板
|
まな板は調理前の生鮮食品が最も頻繁にふれるところ。しかも、長く使っていると包丁でできた傷に菌がたまりやすくなります。
- 熱湯消毒
- 日光にあてて乾燥させる
- 肉、魚、野菜類用など食材によって使い分ける
|
|
ふきん
|
食中毒菌におせんされたふきんで食器や器具をふいたら、せっかくの料理が台無しです。こまめに取り替えましょう。
|
|
包丁
|
意外と水洗いだけですませていることが多くありませんか。刃の部分だけでなく、柄の部分も入念に洗いましょう。
- 柄の部分、刃の付け根も洗剤をつけて念入りに洗う
- 熱湯消毒
|
|
木・竹製の調理器具
|
乾燥しにくいために、菌の温床となりやすいものです。何本かそろえて、乾いたものから使うようにしましょう。
|
|
タワシ、スポンジ
|
洗剤をつけて洗っているから大丈夫、と思っていても、意外に細菌の巣になっています。
|
|
タオル
|
汚れたものを使うと洗う前よりも菌が多くなることがあります。
|
参考
厚生労働省ホームページ(食中毒予防)<外部リンク>