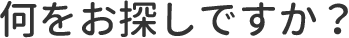本文
令和6年度1月知事定例記者会見(令和7年1月23日)の要旨について
日程:令和7年1月23日(木曜日)
時間:11時27分~12時08分
場所:知事会議室
(南海放送(幹事社))
それでは、会見に移ります。記者クラブからの代表質問は1問です。
南海トラフ巨大地震の発生確率の引き上げについてお伺いします。先般、国の調査委員会が南海トラフ地震の発生確率を引き上げました。また、今月13日には二度目となる南海トラフ地震臨時情報も発表されるなど、県内でも県民の関心が高まっています。
改めて今回の引き上げに対する知事ご自身の受け止めと、県として考えている今後の対応や県民への呼び掛けをお願いいたします。
(知事)
災害で大事なことは、繰り返し申し上げてきたとおり正しく恐れるということでございますので、今回良く誤解されるのが、一気に70パーセントから80パーセントに発生確率が引き上げられたというふうに受け止められてしまうと、正しく恐れるという道筋から外れていくのではないかという点だけは危惧しています。基本的には時期がどんどん経っていくと、確率というのは少しずつ上がっていくと、で、毎年修正するものではなくて、ある程度時期が来て何も起こらなかった場合、ある瞬間からどんと10パーセントずつぐらい上げるとか、そういうものであるということで、今回の引き上げが発表されているということは冷静に受け止めていただけたらと思います。ですから、いつどこで起こるか分からない、確率は高いよというところの原点は、70パーセントの時と今とは変わっていないというふうな受け止めをしていただけたらいいんではないかと思います。
今月15日に、毎年見直しを行っている国の地震調査委員会が発表しているんですけども、南海トラフ地震の30年以内の発生確率について、7年ぶりに70パーセント~80パーセントから80パーセント程度に引き上げたという発表がございました。
今申し上げたように、この発生確率は、想定された地震が発生しない限り、時間の経過とともに年々高くなっていくもので時間予測モデルという手法で計算されています。実際には毎年1パーセント弱ぐらいずつ、発生しなかった場合、日が経ちますから、大体1パーセント弱くらい上がっていくものというふうに思っていただけたら分かりやすいんではなかろうかと思います。確率値の表記が10パーセント単位で丸められているそうであります。ですから、四捨五入なのかそこはちょっと分からないんですけど、上がっていきました。そこで70パーセント~80パーセントから80パーセント程度に引き上げられたというふうなことで、一気に確率値が10パーセント上がったわけではないということでございます。
なお、今回の発表においては、本県への影響が想定される中央構造線断層帯のうち、石鎚山脈北縁区間についても、30年以内の地震発生確率が0.01パーセント以下から0.02パーセント以下に更新をされています。
今回の見直し結果は、発生確率が急激に高まったものということを意味するものではありません。いつ起きてもおかしくない状況に変わりないというふうに受け止めていただけたらと思います。地震調査委員会も、今回の公表において、日本は世界的にみると地震活動が活発で、どの場所においても、地震による強い揺れに見舞われるおそれがある、二つ目に地震は、突然発生し甚大な被害を及ぼす可能性があり、日頃から耐震補強や家具の固定などの対策を講じておくことが重要という注意点を付しているということをお伝えさせていただきます。
また、今月13日の臨時情報ですけれども、南海トラフ地震の発生可能性が高まったとは考えられない現象とされ調査終了となりましたが、ただこれも逆に、大規模災害はいつ、どこで発生するか誰にも分かりませんから、安心するというものではない、ということであります。ある意味では、南海トラフ地震への備えを強化するきっかけとして受け止めていただいて、日頃からの備えを改めて行っていただけたらと思います。
四点ございます。一つ目は、避難場所と避難経路の確認でございます。二つ目は、家族との安否確認手段、日頃から準備をするということ。三つ目は、非常用持出品や家庭における備蓄、これを確認していただくということ。四つ目は、一番けが等々につながりやすい、家具の転倒防止など住宅における安全対策、この四点、これをきっかけにお考え、見つめて、確認していただけたらと思います。
県では、今年度から10年ぶりに被害想定の見直しに着手をしておりまして、能登半島地震等で得た新たな知見も踏まえ、来年度の取りまとめを予定しています。立ち止まることなく大規模地震への備えを進めるため、木造住宅耐震化補助の拡充、あるいは家具等の固定に対する補助制度の創設、住まいの耐震対策事業及び宇和海沿岸地域における津波避難対策事業に集中的に取り組んでいます。これらの事業のさらなる充実強化を図っていきたいと思いますので、積極的に活用していただけたらと思います。
なお、今月17日に発生から30年を迎えた阪神・淡路大震災を振り返る多くの報道がございました。そこを見るにつけ、地震からやはり命を守るには、自助・共助、規模が大きいですから、関係機関が全部の被災地に駆けつけることは不可能であります。初動はほとんどが自助と共助で賄われるという結果があらゆる災害でも示されているとおりでございますので、本県でも同様でございます。ご自身の安全、どうすれば確保できるのか、ご近所同士で助け合う共助の力をどうすれば強めることができるのか。特に、この場合自主防災組織の活動が重要で、その中核として県は日本一を目指して養成してまいりました防災士、2万5千人(※)を超えて日本で一番多い防災士数になりました。こうした皆さんの、何というんですかね、受け止めとチャレンジがいざという時の大きな力になるんではないかというふうに期待をしています。以上です。
(南海放送(幹事社))
ただいまの答弁について、質問がある社はお願いします。
(産経新聞)
すいません、産経新聞です。よろしくお願いいたします。南海トラフに関連してコンビニ業界が最近初めて調査結果を出して、南海トラフが発生したときには約1割の店が1週間程度休業というような調査結果をまとめました。コンビニは、社会インフラの一つと言われてますが、この調査結果に対する受け止めと、さらにこれを受けて備蓄とかの部分で県民に呼び掛けたいことがあれば、お願いします。
(知事)
それぞれの業界ごとに、いざというときの対応をやろうということで調査が進められているという一つの証ではないかなというふうに受け止めています。
その中で大きな役割を果たすコンビニの状況というものが業界内で確認されたというのは非常に意義があるのではないかなというふうに思いますし、災害時の備蓄等々についても特に流通在庫を活用した物資の確保については、県とも協定を結んでいるいろいろな業界が動いてくれていますので、そういう中で常に新たな知見を持って想定をしていくというのは非常に重要なことではないかなというふうに感じました。
先ほど、防災士数2万3千人と言いましたけど、去年の12月時点で2万5千人を超えていますので、訂正させていただきます。
(愛媛新聞)
すいません、愛媛新聞です。よろしくお願いします。先ほど、備えとして住宅の耐震化のお話があったかと思うんですが、今年度、住宅耐震化関係補助金等出されているかと思うんですが、進捗状況等あれば教えてください。
(土木部長)
12月末現在ですけども、耐震診断の派遣を848件申し込みを受けています。耐震の改修設計が297件、耐震改修工事が285件、そういう状況でございます。
(愛媛新聞)
これは例年より進んでるという状況なんでしょうか。
(土木部長)
申し込みはかなり増えております。
(愛媛新聞)
この関係を受けて来年度当初予算等もこれから作られていくと思います。この辺り拡充等お考えあれば教えてください。
(知事)
拡充も含めて、それから途中経過でさらに何ですかね、利用の思いが寄せられた場合は、補正予算も当然視野に入れながら対応していきたいというふうに思っています。
(愛媛新聞)
承知しました。ありがとうございます。
(愛媛新聞)
すいません、愛媛新聞です。一点なんですけれども、石破政権で防災庁を設置しようとしてると思うんですけれども、それについて、知事はどういうふうに考えられて、受け止められてますか。
(知事)
防災というのは、県の仕事においても、一番大事なことは県民の命を守るということですから、最重要課題として県政の課題でも政策課題でも位置付けてきたところでございます。それを一括して考える省庁があるというのは、防災意識の向上にも結び付きますけれども、ただやっぱり本当に国の場合、縦割り行政というものが根付いていますから、本当に機能するための周到な組織図の議論であるとか、あるいは権限であるとか、予算であるとか、やっぱりただつくったら、生まれるものではないと本当に中身のあるものになれば、大きな意義があるんではないかなというふうに期待をしています。
(南海放送)
南海放送です。公助、目に見える公助の部分で言うと、議論だったり、対策というのは結構進んでいるのかなと思うんですけれども、課題としては、自助・共助の部分の意識醸成ではないかなと感じています。
改めて知事としては、この意識醸成のためにどのようなことが必要で、どのような政策も考えているのか教えてください。
(知事)
そうですね。自助というのはもう呼び掛けを続けるという啓発が全てだと思っています。そのためにシェイクアウト訓練であるとか、家庭内における対策であるとか、これはもうくどいほど情報発信をし続けるということが大事かなというふうに思ってます。実際動くときのある程度のバックアップ、それが先ほどの話に出た耐震化の補助制度であるとか、そうしたメニューの政策展開ということになろうかと思います。
共助につきましては、いろんな考え方があるんですが、(知事就任)当初から約10年間追い続けてきたのが、やはり自主防災組織、これは松山市長時代の経験則からだったんですけども、自主防災組織を各地域に組織化していくということ。ただし、松山市長時代にやっていたのですけども、実際あのとき平成13年だったかな。芸予震災という地震が道後地区を襲いまして、そのときに防災士の方々が言っていたのは、機能していたところと機能しなかったところは明暗くっきりだったんですね。機能していなかったところは、防災士であるということを忘れていたというような、いろいろな意見がありました。
そこで大事なことは、防災士の方の意識を高めるということで人数を増やす。そしてまた、そこの横のネットワークを作る。時折、研修等を通じて、訓練に参加していただいてリーダーシップを発揮していただくという、日頃の日常の訓練ですね、こういったことが重要ということを認識していました。
県に来たときに、約10年前に、すぐに防災士を全県でやりたいということを原課に降ろしまして、みんなが一所懸命取り組んでくれた結果、何よりも県民のみなさんがその価値を受け止めていただいたっていうのが一番大きい。役に立とうという社会的な資格なんだと、個人の資格を超えた社会的な資格なんだという意識を持ってトライしていただいたのが、防災士数日本一につながったんではなかろうかというふうに思います。
この方々をフォローしていく。これからは、東京都の人口を考えると、いつまでも1位というのは難しいと思いますから、むしろここからじわじわと増やしていきながらも、質の向上、それから横の連携をここを重視しながら、共助の力を高めていくということが重要ではないかと考えています。
(南海放送(幹事社))
それではよろしいでしょうか。代表質問以外で質問がある社はお願いします。
(朝日新聞)
どうも朝日新聞です。旧優生保護法による不妊手術などを受けた方々に対する補償法が先日施行されましたけれども、改めて愛媛県としての対応についてお聞かせください。
(知事)
はい。まず何よりも、この法律のもとでですね、子供を産み育てる権利を奪われて、心身に多大な苦痛を受けてこられた当事者、そしてご家族のお気持ち、本当におつらいものがあると心から胸が痛みます。法律に基づく国の機関委任事務でございましたけれども、人権上の重大な問題であり、県が法律上執行に関わったことを大変重く受け止めており、県としてもお詫びを申し上げたいと思います。
今回、国が正式に損害賠償責任を認めて補償金等の支給が始まったことは、被害者救済の重要な一歩であり、県としては、対象となる方々が補償金等が受けられるように制度の周知、相談体制の整備等に努めて、被害を受けられた方々に寄り添った対応をしていきたいというふうに思います。
ただ非常に苦労するのはですね、この審査会ですかね、こちらの資料がないんですよ。残ってないんです。国の方で。その中で対象者を探すというのは大変困難なことなのですが、できるだけのことをやって、その情報が当事者の方々に届くように努力はしていきたいというふうに思っています。公表をしていますけども、手術件数というのは、件数だけは把握できているもので545件が確認されているのですが、なんせ全ての資料は国の審査会の方へ行きますので、それがもうほとんどない、残ってないと。最後は平成3年。
(保健福祉部長)
審査会の手術に関しては昭和59年が最後ですが、審査会は県の方で設置をした審査会になります。
(知事)
審査会は59年、同意の方は。
(保健福祉部長)
平成3年です。
(知事)
同意の方は平成3年という、今からもうどちらも30年ぐらい前の資料になるので、本当に残ってない中で、精一杯のことをやらなきゃいけないなというふうに改めて思いを強くしています。
(毎日新聞)
毎日新聞です。よろしくお願いします。
松山市緑町の土砂災害の件なんですけれども、先日17日に復旧工事の住民説明会があって、その中でも住民の方からですね、今、発生メカニズムを検証している技術検討委員会の内容についての疑問とか、また、今度月末に最終回を迎えると思うんですけど、それについて、ちょっと分からないので住民を対象にした説明会を開いてほしいという要望があって、先日、県の方にも、知事宛てに要望書を出したということは、住民の方から聞いているんですけれども、この技術検討委員会を受けた説明会というのを開かれるご予定というのはあるのでしょうか。
(知事)
県の方に来た要望というのが二点ありまして、技術検討委員会において緊急車両用道路との関連性について住民の不安・懸念を解消できる内容とすること、それから道路の検証が未実施の中で議論が可能なのかが分かりづらいという、これが一点です。二つ目は、第4回の後、同委員会による分析内容や今後の対応等について、住民説明会をということなんですが、われわれは県の立場で技術検討委員会も、これは大きな課題だからということで、当初、主体的な権限はなかったんですが、県の方で呼び掛けて、技術検討委員会を作ろうということで、なぜならば規模が大きいので、国の専門家も公平性を担保するために必要ということで、開催をさせていただきました。
ただ、問題なのはですね、道路の方なんですけれども、この技術検討委員会は、あくまでも災害規模の大きさや公平な検討が重要との判断から純粋に技術的な視点で、発生メカニズムの解明、それから再発防止に向けた検討を行うことを目的に県が設置したものでございます。整備された道路そのものの荷重などが土砂災害の発生メカニズムに影響した可能性があるというふうなことについては、これまで委員会で確認されて、公表されていたとおりでございます。
ただ、一方で、道路の設計等になってまいりますと、技術的な視点以外に、例えば、その道路が必要であったか否か、どれぐらいの必要性があったのかどうかとか、あるいは施工・管理に係る経緯、こうした要素については検証が必要になってまいりますけれども、県は道路の設計等には全く関与していないので、資料も何も持っている立場ではないので、これは城山を管理する松山市の役割というふうに認識しております。
このことについては、連絡調整会等を通じて、これまで10回、松山市に対して検証すべき旨を伝えてきたつもりでございます。昨日も市に対して同じように強く要請をさせていただきました。ぜひ、これに真摯に対応して、どういうかたちでやるのか分かりませんけれども、やはり専門家等を入れる検証、もっと早くできたと思うんですけれども、やるべきではないかと個人的には思っています。
それから、技術検討委員会の結果については、これまで県も、全て、逐一公表をしてまいりました。第5回の委員会の結論についても、会終了後、報道機関へ詳細に説明をさせていただくことといたします。現時点では、改めて住民の皆さんに対する説明会を開催する予定は、今の段階ではないんですけれども、ただ、検討結果に対する質問は、常時受け付けをすると。その相談窓口も設けると。設けるというか、連絡がつくようにしておきますので、これまで同様に、丁寧に対応していきたいというふうに思っています。以上です。
(毎日新聞)
その緊急車両用道路のことなんですけど、万が一、技術検討委員会の結果を受けて、松山市が検証しないとなった場合、県としては、それを受け入れるのか、それともまた再び、その検証するように強く求めるのか、それとも県が主導して検証していくのか。そのあたりはいかがでしょうか。
(知事)
常識で考えるとやらないという選択肢はないと思いますけども。
(毎日新聞)
ということは、強く求めていくということですか。松山市が万が一そういう結果を出した場合というのは。
(知事)
そうです。これまでも10回にわたって求めていますので。
(毎日新聞)
分かりました。ありがとうございました。
(愛媛新聞)
すいません。愛媛新聞です。
先ほどの旧優生保護法に関連する質問にちょっと関連するんですけれども、県としては少ない数ですけど、個人が特定できている被害者に対して個別に通知していくという方針に転換されたかと思います。
これまで実施してこなかったという点もあるかと思うんですけど、方針を転換した理由とその意義、それからこれから個別に通知するということはプライバシーに十分配慮した対応、寄り添った対応というのが大切になってくるかと思うんですけれども、留意点や今後の方針など知事のお考えをお聞かせください。
(知事)
はい。これ先ほど申し上げましたように法律に基づいて行われてきた経緯があって、機関委任事務ということで、執行を担ってきたのが都道府県の立場でございました。
これまで対象者のプライバシーには十分に配慮する必要ありと、この保護を考慮して慎重に対応すべきというこれも国の方針でありますが、手術を受けられた方の置かれている状況は、それぞれ非常に複雑でさまざまでございます。
例えば手術を受けたことをご家族の方に伝えていない場合というのもある。あるいは当時のことを思い出したくない、触れて欲しくないというふうなお考えの方々もいらっしゃる。非常に複雑な状況であったことを受けて、個別通知は実施してこなかった経緯がございます。
今後は、今回、法律が正式に制定されて、国の損害賠償責任に基づく補償金というかたちになりました。この性質や国からの協力依頼を踏まえまして、被害に遭われた方に確実にお支払いができるよう、今申し上げたようにプライバシーには十分配慮した上で、個別の通知を実施したいというふうに思っております。
まずは、本当になんせ審査会に資料が何も残っていないという状況なので、所在や連絡先などの調査をしっかりと進めていきたいというふうに思います。
(愛媛新聞)
ありがとうございます。
(あいテレビ)
すいません、あいテレビです。2点ちょっとお聞きしたいことがあります。
一点目はちょっと年末もお聞きしたんですが、原発関連なんですけれども、中国電力が新年度から島根原発の関係で、島根県の自治体の原発関連職員の人件費を年間負担するというような話が出てますが、それについての知事の受け止めと、愛媛も伊方原発があるので、そういったことについてどういうふうにお考えかということをお聞かせいただければと思います。
(知事)
ちょっと島根の場合と愛媛県はずいぶんと話し合いの中身が違うようなので、比較はできないと思うんですね。例えば、島根の場合は、なんていうか、コメントのしようがない、どちらがいい悪いじゃないですよ、人件費については、電力側はそこには税の中に入れないというふうなことで話をしたという経緯があるんで、17パーセントの核燃料税になってると思うんですけども、愛媛県の場合はその人件費も含めて18パーセントになっているということ、それからもう一点の重量割で、島根はないんですよ。愛媛県は重量割で500円から600円に上げたところで、そっちの方が県の入りが多いということの判断もあったんで、個々のやり方が全然違ってるんで、一概に比較はできないんじゃないかなというふうに思ってます。
(あいテレビ)
続けて失礼します。大学の共通テストが終わりました。愛媛県は県庁所在地でしか共通テストが受けられないということで、東予の市町とかからも地元で共通テストが受けられるようにということで要望が出ているようです。
世話人大学で愛媛大学が、基本的には試験会場というのは決めるということなんですが、なかなか今の現状では難しいという回答だったというふうに聞いてます。県庁所在地でしか受けられない県というのが、もう愛媛、佐賀、熊本の3県しかないということで、やっぱり、その受験生の負担を考えても、泊りがけで共通テストを受けるお子さんがいるっていうのは、切実なんじゃないかなと思ってまして、愛媛大学は現状難しいということは、県が尽力できる余地があるんじゃないかなと思いますが、知事はどういうふうにお考えでしょうか。
(知事)
はい。ご案内のとおり、四国中央市、新居浜市、今治市からは、試験会場の選定の任を、これは担うのは愛媛大学になりますので、これは連絡会議の世話大学ということでございます。ここに対して要望があったということでございました。
昨年11月、新居浜市については、現地調査を行ったそうなんですけれども、ふさわしい会場を継続的に確保するめどが立たないと、四国中央市については、試験実施を担当することが見込まれる愛媛大学等から距離が課題であるという理由で、同会議から両市に対して、設置は困難であるとの回答があったということが、報道でも流れたとおりで承知しております。
一方で、昨年6月には宇和島市議会の方でも同様の提案があったと承知しておりまして、この地域、宇和島・南宇和地区県立高校で約250人の受験生がおり、県教委からも、提案の趣旨は十分に理解できると聞いておりまして、さっき言ったように、会場の設置場所・距離、いろいろな課題が、実施する連絡会議の方々の意見で決まっていきますので、県として高校施設等に会場視察等の協力依頼があった場合は、全面的に協力したいと思いますので、当事者の方がやれることが可能性としてあるならば、例えば、こういうことをちょっとサポートしてくれということで、可能であるならば、県としてはやりたいというふうに思ってます。
(愛媛新聞)
すいません、愛媛新聞です。近年の建築の建設費の高騰についてちょっとお伺いしたいんですけれども、一番町・歩行町地区の再開発で、事業計画をいったん見直すというふうに組合から説明を受けています。
一点目が一番町の再開発計画の見直しについての知事の受け止めと、まちづくりへの影響というのを一つお伺いしたいのと、もう一点が県の事業の県民文化会館前の南側の土地も同じように建設費用等の高騰というのが一つ影響して、今、止まってる段階だと思いますので、その活用計画については現状をどう見ているのかと、あと、今後、その後話が進んでるのかどうか、お伺いできればと思います。
(知事)
まず前者からなんですが、ここの会見でも申し上げたとおり、去年、何十年間かけての構想であった、県が担うJRの鉄道高架事業が完成を見ました。これをぜひ県都には生かしていただきたい、まちづくりに生かしていただきたいという本当に願いがございます。できれば同時並行で動いて、姿かたちが周辺整備にも見えたら、良かったなというふうに思うんですけど、もう終わったことは仕方がないので、今後もう本当にスピードアップして、まちづくりのビジョンを明確に位置付けて進めていただきたいなと心から願っています。県都の発展なくして愛媛県の発展はないというふうに思いますので、ぜひ期待をしたいと思っています。
その中で危惧しているのは、JRの周辺駅前開発と、それからこれも長年にわたって放置状態になっている国際ホテルの跡地の問題、跡地というかまだ今、建物がありますからそれをどうするのか、それからL字開発の問題と、重要な拠点の整備がまだ見えないという段階ではないかなというふうに捉えています。
そういう中で、国際ホテルについては一時、県にも協力要請があったので、県のもしものときに県がこれぐらい応援できるよというふうなことで、市から相談があったときにお答えした経緯がありました。
それで十分いけますというふうなことだったんで、期待をしていたんですけれども残念ながら事業者の判断でこれが頓挫をしたというのは後でお聞きしましたので、これは本当に残念に思っています。その経緯については、私は交渉の立場にいなかったので分かりませんけれども残念でした。その後しばらく放置状態が続いて、組合の方で新たな事業の計画が、発表があったんですけども、そもそもあそこは都市計画決定していますから、松山市の関与というものをより強めないとなかなか難しいんじゃないかなと。
ただL字にしても、国際ホテルにしても、もっと踏み込む必要があるんじゃないかなというのは個人的には感じます。というのは、かつてロープウェイ街の整備を担ったときには、かなり市が踏み込んで住民の皆さんと対話を積み重ねて、ワークショップを開いたり、本当に3年間の工事期間で売り上げ減少するのも覚悟できるんですかというような、さまざまなやり取りを乗り越えて、一気にやった経緯がございますので、かなり市が主導しないと難しいんではないかなというふうに今回も思いましたので、ぜひ今後の展開を期待したいと思います。
はい。それと県文ですね、県文については、これはもう前に申し上げたとおりですね、ちょっと欲張りすぎた条件だったかなということは反省をしています。というのはMICE機能、いろんな意見を頂戴する中で今愛媛県には、宴会場もない、グレードの高い宿泊施設もないというのは、地方都市としてすごく弱みになってきているので、そういったことも踏まえて県民文化会館の活用も踏まえたMICE機能の整備というのがいいんじゃないかとていう意見が一番多く寄せられたので、それに基づいて投げ掛けたんですけれども、MICE機能の施設についても、民間投資で何とかできないかなというちょっと欲張った面もありました。
そこが、事業者からすれば、収益を生まない設備になりますので、条件的に若干の足かせになったこともあったのかなと思いますけど、その中で建設費高騰等も襲ってきましたので、収益の見通しというのが立てにくいというふうなことで、当面中止を発表させていただいた次第でございます。ただ、その後、場所はいいということは確認できました。というのは、やはり多くの方々が関心を持ってくれたということで、条件をどうすればいいのかというようなことも踏まえて、いろいろな案を練っています。
個別にこんなんだったらどうなのかな、こんなんだったらどうなのかなっていうような業界単位でのご意見なんかも参考にさせていただきながら、やがてそういった条件をベースに、公平なプロポーザル方式の投げ掛けをしていきたいなというふうに思ってますので、可能な限りスピーディーにやっていきたいと思っています。
(愛媛新聞)
すいません、続けて同じ関連なんですけど、一点、建設費の高騰の影響というのがあったと思うんですけれども、今、南町、県民文化会館の南側の土地は、場所は良いというふうには言われて、具体的に例えば、県がどの程度補助できれば、事業者側からですね、賛同を得るというか納得する提案が出してもらえるのかとか。
(知事)
何となく、分かんないですよ、例えば一番やっぱりMICE機能を民間で何とかやれないかっていうところが収益を生まないがゆえに、難しいのかなというような感じはするんですよね。だからもうMICE機能はMICE機能で、県民文化会館をちょっとテコ入れして、県の方でやるとかですね、そういう役割分担というのも一つの方法かなというふうな感じはしてます。
(愛媛新聞)
ありがとうございました。
(読売新聞)
読売新聞です。先日、文化庁からですね内定交付がありました国民文化祭についてなんですけども、2点お伺いしたいんですけれども、令和10年秋の開催予定ということで令和10年が西日本豪雨発生から10年の年になるということで、テーマとしては復興というものを掲げていくのか、ということと、もう一点、愛媛県で開催した場合、どれくらいの費用がかかるのか、ということをお伺いしたいです。
(知事)
まだ、これからどういうコンセプトでどんな文化祭をするかというのは、私が決めるものではないですから、関係者に集まっていただいて、議論していただいて、基本構想を作っていくっていうのが来年になりますので、この段階でどうするということは申し上げることはできません。ただ、非常にタイミング的にいいかなと思うのは、東京藝術大学と連携協定を結んでアートベンチャーエヒメフェス2025を今年の秋、いよいよ第1回をスタートいたします。毎年というのはちょっとしんどいっていうことで、3年に一遍くらい開催しようっていうようなことが準備期間、それからきっかけづくりに非常にいいタイミング、スケジュール感ではないかということで提案いただきました。
日比野学長の方から、では1回目はまずやると。3年後の2回目の時に、さらにグレードアップさせるために、国民文化祭と連動させたら一気に文化芸術の開花が期待できるんじゃないかというふうなことで提案もいただき、交渉に入りました。まさに狙いどおり令和10年、誘致、文化庁の方が内定いただいたので、これは四十数日間に及ぶ長いイベントになります。交流人口でいうと百何十万人というすごい規模になりますんで、参加者も3分の2が県内の関係者、3分の1が県外からの関係者ということで、非常にバラエティーに富んだ文化芸術の祭典になるというふうに思います。
もちろん、費用も3年前から準備しまので、4年かけて準備に当たっていかなければなりません。先催県、毎年いろいろどこかでやっていますけれども、最近の開催経費を聞いてみると、一概には言えませんけども、だいたい4年間の平均事業費が10億円から11億円、そのうち国費が3億円程度、県費が8億円程度というような感じの予算配分のようでございます。ここから、協賛金であるとか、市町負担であるとかいろいろいろなものが入ってきますので、まだこの段階では詰め切れていないです。
(南海放送(幹事社))
時間もありますので、他にございませんでしょうか。それではこれで会見を終わります。
(※)会見では2万3千人と発言
※議事録については、読みやすさや分かりやすさを考慮し、発言の趣旨等を損なわない程度に整理しております。