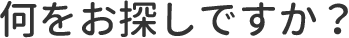本文
インド経済交流ミッションの記者発表の要旨について
【記者発表】
日時:令和7年1月23日(木曜日) 11時00分~11時20分
場所:知事会議室
(南海放送(幹事社))
それでは時間になりましたので始めます。本日は県から発表事項が2件あると伺っています。まず、インド経済交流ミッションについて、よろしくお願いします。
(知事)
県では、県内の経済団体と連携しまして、2月2日の日曜日から7日の金曜日の日程で、昨年1月に続きまして、2回目となるインド経済交流ミッションを実施し、前回のミッションで経済協力に関する覚書を締結いたしましたタミルナドゥ州、今回はもうここだけを訪問することといたします。訪問団規模は、経済界から非常にビジネスあるいは将来の人員確保に関して関心が非常に高い声が寄せられておりまして、前回70名規模でミッション団が組まれましたけれども、今回はそれを上回る80名程度のミッション団となる予定でございます。
前回のミッション以降、インド国内2位の経済規模を誇り、県内ものづくり企業と親和性の高い産業を擁するタミルナドゥ州とのLocal to Localの交流基盤、そして南部最大規模の財閥ムルガッパグループとの強固な人脈を礎にしまして、それ以来、現地に精通するアドバイザーの豊富な知見や人脈と、昨年5月に将来のことを考えて開設しました、愛媛県のサポートデスクによる、機動的できめ細やかなサポート等を最大限に活用しながら、県内企業のビジネス機会の創出と人材確保、これを両輪に取り組んでまいりました。
世界最大規模の人口を誇りますが、県内にはインドの方は91名とまだまだ人材確保にもいたっておりません。そういったところできっかけをつかむのが去年の訪問の役割でありましたけれども、計り知れない可能性を感じる一方で、一定のリスクを秘めたインドへの挑戦は手探りの状態でのスタートでありましたけれども、前回のミッションを契機に、県内企業と現地企業とのビジネス連携、そして人材確保の動きが進展しております。
また、県内企業のインドビジネスへの意欲と関心も着実に高まってきております。これらを追い風に、県としては初めてとなりますが、2年連続のミッションを行って、インドとの経済交流を一層加速させることが今回の狙いでございます。
今回のミッションのテーマは主に三つございます。
一つは県内企業への幅広い商談機会の創出でございます。タミルナドゥ州やムルガッパグループ等との連携に加え、アドバイザーのネットワークを駆使しまして、本県企業に関心のある現地企業の参加を得まして、初めて県内企業がブースを設置しての商談会を実施したいと思っております。この商談会には、インドでのビジネスに意欲を持つ愛媛県内の企業は12社が参加予定でございます。新規取引の開拓や協業等につながる具体的な商談に結び付けることができればと願っております。
二つ目は、インド人材の受け入れ促進でございます。インド人材受け入れを目指す県内企業や留学生交流を進めたいという思いを持つ愛媛大学とともに、本県の産業や愛媛で働くことの魅力、生活環境などの情報の発信やインド人材と参加企業との交流、将来的な人的交流の拡大に向けた関係者間の協議を行う予定でございます。
三つ目は、将来的な県産品輸出を見据えた食の魅力発信でございます。インドへの食品輸出は煩雑な手続き、またコールドチェーンの未発達など越えなければならないハードルは、現段階では高いものがありますが、中長期的な視点で見ますと、世界最大規模の市場を持つということもありますので、トライをしていきたい重要なテーマでございます。国内の市場がやがて縮小傾向に入るということを考えますと、積極的に大きな市場への挑戦をするということは、未来を切り開いていくためには欠かせない行動でございます。
こうした中、県産の水産物の販路開拓の可能性が見いだせたことから、今回、在チェンナイ日本国総領事館の協力を得られることができましたので、総領事の公邸をお借りいたします。ここに現地の有力者等をお招きしまして、水産物を中心に現地で調理したメニューの提供と、PRを関係者に行いたいと思います。
さらにタミルナドゥ州政府やムルガッパグループのキーマンと面会しまして、人脈のさらなる強化を図るほか、新たにタミルナドゥ州全域を管轄する商工会議所であり、会員企業700社の国際的なビジネスネットワーク拡大に向け、本県との連携に前向きな気持ちを寄せていただいておりますマドラス商工会議所とミーティングを行いまして、今後のビジネスマッチング支援などに向けた新たな交流基盤の構築を図ることとしております。
今回のミッションは、インドとの経済交流におけるホップ・ステップ・ジャンプのステップと位置付け、将来を見据えた新たな挑戦にも踏み出しながら、5年先10年先の大きな飛躍につなげるための確かな一歩としたいと思います。以上です。
(南海放送(幹事社))
ただ今の発表事項に関して、質問のある社はお願いします。
(読売新聞)
読売新聞です。よろしくお願いします。
2年連続での同一国への派遣ということなんですけれども、昨年、実際どういう効果があったというふうに認識されていますか。
(知事)
さっき申し上げたように昨年の時点で91人の方、愛媛県にはもうすでに1万5000人の外国人の方が来られておりますけれども、一番多いベトナムの技能実習生は2700人、全部で5000人近くの方がいらっしゃいますが、その10倍規模の人口を誇るインドの方は91人という現状で、非常に、工科大学等々、各地域にそろっていまして、豊富な人材を擁しているんだけれども、なかなか、つてがなかったということもありまして、昨年のミッションでは、ともかくきっかけを作るというのが目的でありました。
経済界も、非常にやはり将来のことを人材確保、今苦慮していますから、技能実習生を中心に何とかきっかけを作りたいという思いが強くてですね、本当に70名のミッションというのはかなり大がかりだったと思いますけれども、そうした関心の表れだったと思います。
そこでアドバイザーを、インドに精通するアドバイザーに協力をいただきまして、インドというのは20数州あるんですけども、全ての州で法律が異なって、言葉が異なって、慣習が異なると、一つ一つの州が国のような感じなんですね。商慣習も全然違いますから愛媛県の産業構造なんかを踏まえました親和性、こうしたことと対日関係の環境がいいというようなところを選ぶ必要があるということを考えていたときに、アドバイザーから、タミルナドゥ州が一番ベストだろうという提案をいただきました。
人脈を持たれていますから、政府との交渉、それからやはりパートナーが重要でありますから、先ほどご紹介したムルガッパグループという財閥を紹介していただきまして、私も直接お会いしてまいりました。そことの信頼関係が構築できましたので、協定を結ぶことを通じてきっかけが生まれました。以来、サポートデスクを置いて、インドに関心のある企業のサポートを愛媛県の方でしようということだったんですが、かなり問い合わせも多くございまして、非常に関心が高まっているというのを実感しております。今回、その市場規模と可能性を含めて、一つのきっかけが生まれた後に、大きく何て言うんですかね、こう、関係が濃くできる可能性が実感できましたので、経済界にお話をしたところ、昨年以上の訪問をしたいという声が寄せられましたので、タイミングとしては、もう今回2年連続というのはベストではないかなという判断をいたしました。
今回、前回で培った人脈、きっかけ、そしてその後の1年間で下準備をしてきた状況が商談会の開催等々に結び付いたということになりますので、本当に将来の愛媛県の企業の人材確保や、ビジネスチャンスに結び付ければというふうに思っています。
(読売新聞)
ありがとうございます。ちょっと追加でお伺いしたいんですけれども県内企業12社と現地企業の商談会も実施することなのですけど、県内企業は主に水産業になるんですか。どういった業態になるのか。
(知事)
水産業というのは先ほど申し上げた食のPRで、領事公邸を場所としてお借りして行うものなのですが、ものづくりが中心です。ビジネスマッチングの方は。やはり愛媛県には、ものづくりの技術を持った会社がたくさんありますので、こうしたところが中心になります。
(読売新聞)
例えば繊維だったり造船だったりと業態でいうと。
(知事)
まず今までですね、サポートデスクを5月に開設したのですけれども、そこにぜひ相談したいというふうに県内企業からお声を頂戴しているのが、今、活用中、これをこのサポートデスクを活用中の会社が15社、すでにございます。
今回の12社につきましては、一部サポートデスクの支援企業と重複しますけれども、排水処理エネルギー回収システムの技術を持った会社であるとか、リチウムイオンバッテリー用のセパレーターの成膜製造設備を作っている会社であるとか、精密機械加工の会社であるとか、鮮度の保持フィルムの会社であるとか、結構やっぱり東予地域のものづくり産業やあるいは商談会に参加で、食で言うと、だしの素の会社、それからタオル、真珠、こういったところが1社ずつあるという状況でございます。
(読売新聞)
すいませんありがとうございました。
(愛媛新聞)
愛媛新聞です。昨年からの成果という部分でサポートデスク活用中15社というお話ありますけども、もう少し言える範囲でビジネス機会の創出という部分でどういった部分が成果が出てるのかとかですね、あと人材の受け入れでどのようなちょっと成果出ているのか、伺います。
(知事)
実はこれまでもそうなんですけども、食なんかを売り込む場合は割と早く実績、売り上げというのは上がるんですが、ものづくりの場合は、あのサンプルでの試験であるとか、かなり綿密な、工程が必要になってまいります。ですから契約に結び付けるには2年、3年はかかるというのがこれまでどこの国でやっても同じような経過でありますから、まさに商談会というのが一つの大きなきっかけになると思いますので、これからになってくると思います。
商談会、県が介在する商談会のメリットっていうのが一つありまして、こうしたアジア各国に行ったときに、やはり良い企業、それからちょっとどうなのかなっていう企業が混在しています。単独で会社が行った場合はですね、そこの見分けがつかない、あるいはそこの調査に膨大な労力がかかるんですが、県がやる場合は向こうの州と連携協定を結んでいますから、こちらはこちらで今回のミッション団のようにしっかりとした会社、技術力を持った会社をセレクトして商談会のメンバーとして派遣できると、同様に向こう側もですね、政府がしっかりとフィルターにかけた会社が選ばれて出てきますので、いわば信用調査のステップアップ、ジャンプアップができるという、これが最大のメリットだと思います。
ですから、この県内企業これまで各国でやってきましたので、その信頼というものが生まれていますから、12社、未開の地でもありますけれども、県も関係した商談会ならば安心していけるというふうなことで、一気に12社が参加するということになったんではなかろうかと思います。
人材についてはこれもまた、協定を結びましたけども、送り出し機関でのトレーニングの問題、それからこちら側の受け入れの問題、これもこちら側、実績がありますので準備に入っています。こうしたことを積み上げて、やがては技能実習生の招聘(しょうへい)に結び付けることができるんではなかろうかと思っています。
(愛媛新聞)
商談会の方は現地企業は何社ぐらい参加しそうでしょうか。
(知事)
マッチング予定数は今のところ1社当たり、12社参加しますので、3件ぐらいを向こうは準備するということなので、36件を予定しています。非常に大雑把ですけど、12社かける3件で、36件ぐらいの話し合いができればいいんじゃないかなというふうに思っています。
(愛媛新聞)
こうした現地との経済交流なのですけども、愛媛以外にも、タミルナドゥ州との連携強化を狙う地方自治体、結構多くいるかと思います。そうした中で、愛媛県としてどうやって競争に勝ち残っていきたいとか。
(知事)
他の県がどうやっているか分かりません。営業本部みたいなかたちもうちしかないですから。ただ単に協定を結んで、日系のデパートみたいなところで、何とかフェアやって、テープカットして終わりというところもありますので、うちの場合はそういったことはあまり関心がなくてですね、地に足のついた営業活動が愛媛県方式なので、あくまでも実績数字にこだわって展開をしてますから、ちょっと一概に比較はできないんじゃないかなというふうに思います。
(愛媛新聞)
そのあたり営業活動っていうのを強みにして。
(知事)
そうですね、はい。
愛媛県のように営業本部で、何件訪問し、どれだけの商談が成立し、どれだけの件数、ビジネスマッチングが行われて、新規成約がいくらと発表しているところが、そもそも愛媛県以外ありません。
(NHK)
NHKです。先ほどの12社の件なんですけども、ものづくり企業といっても、多様な商品を扱うように思うんですが、企業側から聞こえる期待の声だとか狙いのようなものがあればお伺いできますでしょうか。
(知事)
やはり共通しているのはやっぱり人口10数億という世界最大人口を抱えるインドで成長が著しい経済情勢、そのやっぱり市場の大きさと成長力というものに対する期待感というのは非常に大きいのではないかなというふうに思っています。
(NHK)
ありがとうございます。あと一点、食の件なんですけども、水産業のところで可能性を見い出せてきたというお話ありました。一方でコールドチェーン未発達というハードルもあるということなのですが、そのあたりどういうふうに超えて今、可能性の段階にきているのかっていう。
(知事)
そうですね。これはもうこれからの話なのですけれども、要はその、冒頭に申し上げたとおり、単独で突っ込んでいってもなかなか小売店舗まで展開することは難しい。ということは財閥のいいパートナーが見つけられるかどうかが一つの成功の鍵を握ってくると思います。ここはいろいろな面での会社を持っていますしグループですから、そこでのいろいろな人脈や販売ネットワーク、現地での信頼、こうしたものを持っているというところとの信頼関係が結ばれれば早く入っていけるのではないかというふうに思っていますので、ここは非常に当初行くときにもいいパートナーをぜひ見つけて欲しいということにもこだわったのはこの点がございます。
(NHK)
ありがとうございます。県としては特に水産業だけというわけではなくても多様な業種産業でサポートしていく。
(知事)
もちろんそうです。はい。
(NHK)
ありがとうございます。
(知事)
インドというのは、まだ日本食レストランそのものはまだ400店舗と少ないんですけれども、どんどん今増えてきているという状況だそうですので、特にかなり経済成長と同時に富裕層も増えてきていますから、そこを中心にやっぱり日本の寿司なんかへの関心が高まってきているので。この日本食レストラン向けに販売し始めた現地卸売業者と結び付くことができたというので、今回、一気にやろうというふうなことになったことを申し添えさせていただきます。
※議事録については、読みやすさや分かりやすさを考慮し、発言の趣旨等を損なわない程度に整理しております。
日時:令和7年1月23日(木曜日) 11時00分~11時20分
場所:知事会議室
(南海放送(幹事社))
それでは時間になりましたので始めます。本日は県から発表事項が2件あると伺っています。まず、インド経済交流ミッションについて、よろしくお願いします。
(知事)
県では、県内の経済団体と連携しまして、2月2日の日曜日から7日の金曜日の日程で、昨年1月に続きまして、2回目となるインド経済交流ミッションを実施し、前回のミッションで経済協力に関する覚書を締結いたしましたタミルナドゥ州、今回はもうここだけを訪問することといたします。訪問団規模は、経済界から非常にビジネスあるいは将来の人員確保に関して関心が非常に高い声が寄せられておりまして、前回70名規模でミッション団が組まれましたけれども、今回はそれを上回る80名程度のミッション団となる予定でございます。
前回のミッション以降、インド国内2位の経済規模を誇り、県内ものづくり企業と親和性の高い産業を擁するタミルナドゥ州とのLocal to Localの交流基盤、そして南部最大規模の財閥ムルガッパグループとの強固な人脈を礎にしまして、それ以来、現地に精通するアドバイザーの豊富な知見や人脈と、昨年5月に将来のことを考えて開設しました、愛媛県のサポートデスクによる、機動的できめ細やかなサポート等を最大限に活用しながら、県内企業のビジネス機会の創出と人材確保、これを両輪に取り組んでまいりました。
世界最大規模の人口を誇りますが、県内にはインドの方は91名とまだまだ人材確保にもいたっておりません。そういったところできっかけをつかむのが去年の訪問の役割でありましたけれども、計り知れない可能性を感じる一方で、一定のリスクを秘めたインドへの挑戦は手探りの状態でのスタートでありましたけれども、前回のミッションを契機に、県内企業と現地企業とのビジネス連携、そして人材確保の動きが進展しております。
また、県内企業のインドビジネスへの意欲と関心も着実に高まってきております。これらを追い風に、県としては初めてとなりますが、2年連続のミッションを行って、インドとの経済交流を一層加速させることが今回の狙いでございます。
今回のミッションのテーマは主に三つございます。
一つは県内企業への幅広い商談機会の創出でございます。タミルナドゥ州やムルガッパグループ等との連携に加え、アドバイザーのネットワークを駆使しまして、本県企業に関心のある現地企業の参加を得まして、初めて県内企業がブースを設置しての商談会を実施したいと思っております。この商談会には、インドでのビジネスに意欲を持つ愛媛県内の企業は12社が参加予定でございます。新規取引の開拓や協業等につながる具体的な商談に結び付けることができればと願っております。
二つ目は、インド人材の受け入れ促進でございます。インド人材受け入れを目指す県内企業や留学生交流を進めたいという思いを持つ愛媛大学とともに、本県の産業や愛媛で働くことの魅力、生活環境などの情報の発信やインド人材と参加企業との交流、将来的な人的交流の拡大に向けた関係者間の協議を行う予定でございます。
三つ目は、将来的な県産品輸出を見据えた食の魅力発信でございます。インドへの食品輸出は煩雑な手続き、またコールドチェーンの未発達など越えなければならないハードルは、現段階では高いものがありますが、中長期的な視点で見ますと、世界最大規模の市場を持つということもありますので、トライをしていきたい重要なテーマでございます。国内の市場がやがて縮小傾向に入るということを考えますと、積極的に大きな市場への挑戦をするということは、未来を切り開いていくためには欠かせない行動でございます。
こうした中、県産の水産物の販路開拓の可能性が見いだせたことから、今回、在チェンナイ日本国総領事館の協力を得られることができましたので、総領事の公邸をお借りいたします。ここに現地の有力者等をお招きしまして、水産物を中心に現地で調理したメニューの提供と、PRを関係者に行いたいと思います。
さらにタミルナドゥ州政府やムルガッパグループのキーマンと面会しまして、人脈のさらなる強化を図るほか、新たにタミルナドゥ州全域を管轄する商工会議所であり、会員企業700社の国際的なビジネスネットワーク拡大に向け、本県との連携に前向きな気持ちを寄せていただいておりますマドラス商工会議所とミーティングを行いまして、今後のビジネスマッチング支援などに向けた新たな交流基盤の構築を図ることとしております。
今回のミッションは、インドとの経済交流におけるホップ・ステップ・ジャンプのステップと位置付け、将来を見据えた新たな挑戦にも踏み出しながら、5年先10年先の大きな飛躍につなげるための確かな一歩としたいと思います。以上です。
(南海放送(幹事社))
ただ今の発表事項に関して、質問のある社はお願いします。
(読売新聞)
読売新聞です。よろしくお願いします。
2年連続での同一国への派遣ということなんですけれども、昨年、実際どういう効果があったというふうに認識されていますか。
(知事)
さっき申し上げたように昨年の時点で91人の方、愛媛県にはもうすでに1万5000人の外国人の方が来られておりますけれども、一番多いベトナムの技能実習生は2700人、全部で5000人近くの方がいらっしゃいますが、その10倍規模の人口を誇るインドの方は91人という現状で、非常に、工科大学等々、各地域にそろっていまして、豊富な人材を擁しているんだけれども、なかなか、つてがなかったということもありまして、昨年のミッションでは、ともかくきっかけを作るというのが目的でありました。
経済界も、非常にやはり将来のことを人材確保、今苦慮していますから、技能実習生を中心に何とかきっかけを作りたいという思いが強くてですね、本当に70名のミッションというのはかなり大がかりだったと思いますけれども、そうした関心の表れだったと思います。
そこでアドバイザーを、インドに精通するアドバイザーに協力をいただきまして、インドというのは20数州あるんですけども、全ての州で法律が異なって、言葉が異なって、慣習が異なると、一つ一つの州が国のような感じなんですね。商慣習も全然違いますから愛媛県の産業構造なんかを踏まえました親和性、こうしたことと対日関係の環境がいいというようなところを選ぶ必要があるということを考えていたときに、アドバイザーから、タミルナドゥ州が一番ベストだろうという提案をいただきました。
人脈を持たれていますから、政府との交渉、それからやはりパートナーが重要でありますから、先ほどご紹介したムルガッパグループという財閥を紹介していただきまして、私も直接お会いしてまいりました。そことの信頼関係が構築できましたので、協定を結ぶことを通じてきっかけが生まれました。以来、サポートデスクを置いて、インドに関心のある企業のサポートを愛媛県の方でしようということだったんですが、かなり問い合わせも多くございまして、非常に関心が高まっているというのを実感しております。今回、その市場規模と可能性を含めて、一つのきっかけが生まれた後に、大きく何て言うんですかね、こう、関係が濃くできる可能性が実感できましたので、経済界にお話をしたところ、昨年以上の訪問をしたいという声が寄せられましたので、タイミングとしては、もう今回2年連続というのはベストではないかなという判断をいたしました。
今回、前回で培った人脈、きっかけ、そしてその後の1年間で下準備をしてきた状況が商談会の開催等々に結び付いたということになりますので、本当に将来の愛媛県の企業の人材確保や、ビジネスチャンスに結び付ければというふうに思っています。
(読売新聞)
ありがとうございます。ちょっと追加でお伺いしたいんですけれども県内企業12社と現地企業の商談会も実施することなのですけど、県内企業は主に水産業になるんですか。どういった業態になるのか。
(知事)
水産業というのは先ほど申し上げた食のPRで、領事公邸を場所としてお借りして行うものなのですが、ものづくりが中心です。ビジネスマッチングの方は。やはり愛媛県には、ものづくりの技術を持った会社がたくさんありますので、こうしたところが中心になります。
(読売新聞)
例えば繊維だったり造船だったりと業態でいうと。
(知事)
まず今までですね、サポートデスクを5月に開設したのですけれども、そこにぜひ相談したいというふうに県内企業からお声を頂戴しているのが、今、活用中、これをこのサポートデスクを活用中の会社が15社、すでにございます。
今回の12社につきましては、一部サポートデスクの支援企業と重複しますけれども、排水処理エネルギー回収システムの技術を持った会社であるとか、リチウムイオンバッテリー用のセパレーターの成膜製造設備を作っている会社であるとか、精密機械加工の会社であるとか、鮮度の保持フィルムの会社であるとか、結構やっぱり東予地域のものづくり産業やあるいは商談会に参加で、食で言うと、だしの素の会社、それからタオル、真珠、こういったところが1社ずつあるという状況でございます。
(読売新聞)
すいませんありがとうございました。
(愛媛新聞)
愛媛新聞です。昨年からの成果という部分でサポートデスク活用中15社というお話ありますけども、もう少し言える範囲でビジネス機会の創出という部分でどういった部分が成果が出てるのかとかですね、あと人材の受け入れでどのようなちょっと成果出ているのか、伺います。
(知事)
実はこれまでもそうなんですけども、食なんかを売り込む場合は割と早く実績、売り上げというのは上がるんですが、ものづくりの場合は、あのサンプルでの試験であるとか、かなり綿密な、工程が必要になってまいります。ですから契約に結び付けるには2年、3年はかかるというのがこれまでどこの国でやっても同じような経過でありますから、まさに商談会というのが一つの大きなきっかけになると思いますので、これからになってくると思います。
商談会、県が介在する商談会のメリットっていうのが一つありまして、こうしたアジア各国に行ったときに、やはり良い企業、それからちょっとどうなのかなっていう企業が混在しています。単独で会社が行った場合はですね、そこの見分けがつかない、あるいはそこの調査に膨大な労力がかかるんですが、県がやる場合は向こうの州と連携協定を結んでいますから、こちらはこちらで今回のミッション団のようにしっかりとした会社、技術力を持った会社をセレクトして商談会のメンバーとして派遣できると、同様に向こう側もですね、政府がしっかりとフィルターにかけた会社が選ばれて出てきますので、いわば信用調査のステップアップ、ジャンプアップができるという、これが最大のメリットだと思います。
ですから、この県内企業これまで各国でやってきましたので、その信頼というものが生まれていますから、12社、未開の地でもありますけれども、県も関係した商談会ならば安心していけるというふうなことで、一気に12社が参加するということになったんではなかろうかと思います。
人材についてはこれもまた、協定を結びましたけども、送り出し機関でのトレーニングの問題、それからこちら側の受け入れの問題、これもこちら側、実績がありますので準備に入っています。こうしたことを積み上げて、やがては技能実習生の招聘(しょうへい)に結び付けることができるんではなかろうかと思っています。
(愛媛新聞)
商談会の方は現地企業は何社ぐらい参加しそうでしょうか。
(知事)
マッチング予定数は今のところ1社当たり、12社参加しますので、3件ぐらいを向こうは準備するということなので、36件を予定しています。非常に大雑把ですけど、12社かける3件で、36件ぐらいの話し合いができればいいんじゃないかなというふうに思っています。
(愛媛新聞)
こうした現地との経済交流なのですけども、愛媛以外にも、タミルナドゥ州との連携強化を狙う地方自治体、結構多くいるかと思います。そうした中で、愛媛県としてどうやって競争に勝ち残っていきたいとか。
(知事)
他の県がどうやっているか分かりません。営業本部みたいなかたちもうちしかないですから。ただ単に協定を結んで、日系のデパートみたいなところで、何とかフェアやって、テープカットして終わりというところもありますので、うちの場合はそういったことはあまり関心がなくてですね、地に足のついた営業活動が愛媛県方式なので、あくまでも実績数字にこだわって展開をしてますから、ちょっと一概に比較はできないんじゃないかなというふうに思います。
(愛媛新聞)
そのあたり営業活動っていうのを強みにして。
(知事)
そうですね、はい。
愛媛県のように営業本部で、何件訪問し、どれだけの商談が成立し、どれだけの件数、ビジネスマッチングが行われて、新規成約がいくらと発表しているところが、そもそも愛媛県以外ありません。
(NHK)
NHKです。先ほどの12社の件なんですけども、ものづくり企業といっても、多様な商品を扱うように思うんですが、企業側から聞こえる期待の声だとか狙いのようなものがあればお伺いできますでしょうか。
(知事)
やはり共通しているのはやっぱり人口10数億という世界最大人口を抱えるインドで成長が著しい経済情勢、そのやっぱり市場の大きさと成長力というものに対する期待感というのは非常に大きいのではないかなというふうに思っています。
(NHK)
ありがとうございます。あと一点、食の件なんですけども、水産業のところで可能性を見い出せてきたというお話ありました。一方でコールドチェーン未発達というハードルもあるということなのですが、そのあたりどういうふうに超えて今、可能性の段階にきているのかっていう。
(知事)
そうですね。これはもうこれからの話なのですけれども、要はその、冒頭に申し上げたとおり、単独で突っ込んでいってもなかなか小売店舗まで展開することは難しい。ということは財閥のいいパートナーが見つけられるかどうかが一つの成功の鍵を握ってくると思います。ここはいろいろな面での会社を持っていますしグループですから、そこでのいろいろな人脈や販売ネットワーク、現地での信頼、こうしたものを持っているというところとの信頼関係が結ばれれば早く入っていけるのではないかというふうに思っていますので、ここは非常に当初行くときにもいいパートナーをぜひ見つけて欲しいということにもこだわったのはこの点がございます。
(NHK)
ありがとうございます。県としては特に水産業だけというわけではなくても多様な業種産業でサポートしていく。
(知事)
もちろんそうです。はい。
(NHK)
ありがとうございます。
(知事)
インドというのは、まだ日本食レストランそのものはまだ400店舗と少ないんですけれども、どんどん今増えてきているという状況だそうですので、特にかなり経済成長と同時に富裕層も増えてきていますから、そこを中心にやっぱり日本の寿司なんかへの関心が高まってきているので。この日本食レストラン向けに販売し始めた現地卸売業者と結び付くことができたというので、今回、一気にやろうというふうなことになったことを申し添えさせていただきます。
※議事録については、読みやすさや分かりやすさを考慮し、発言の趣旨等を損なわない程度に整理しております。