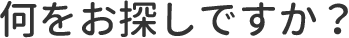本文
令和6年度12月知事定例記者会見(令和6年12月26日)の要旨について
日程:令和6年12月26日(木曜日)
時間:11時26分~12時13分
場所:知事会議室
(愛媛新聞(幹事社))
それでは会見に移ります。記者クラブからの代表質問は1問です。松山空港国際線のさらなる利用促進についてお伺いします。
松山空港の国際線は、旺盛なインバウンド需要による好調な搭乗率を背景に、今年度も増便が相次ぎました。10月27日からはソウル線が週14便、釜山線が週6便、台北線が週3便に増便されましたが、どのような効果が得られているのか教えてください。
また増便に伴い国際線の利用者数も大幅に増加していると思いますが、国際線の更なる利用促進に向けた、知事のお考えもお聞かせください。
(知事)
まず、運航中の松山空港国際線は、各航空会社から高い搭乗率への評価をいただきまして、10月末には過去最多の週23便へと大幅増便されましたが、11月の搭乗率はソウル線が9割、釜山線と台北線が8割、それぞれ超えておりまして、12月も同水準で推移していますので、好調が続いている段階でございます。
このため、今年度の国際線利用者数は、過去最高であった昨年度、13万6千人を大きく超える2倍以上の29万人に達するのではないかと見込んでおりまして、今年の外国人延宿泊者数においても、これまでの最多は平成30年の23万人でございましたが、これを大きく上回る40万人近くになるのではないかと推計しております。
いろいろと戦略的に取り組んでまいりましたので、例えば釜山線のゴルフ人口のマーケットとか、いろんな課題、それからソウル線については、特に東予や南予も含めた愛媛県全体の魅力のPR、いろんな取り組みをしてます。そういう中でゴルフ場や宿泊施設、飲食店関係者からは、インバウンド客の増加に対する喜びの声が県の方にも届いておりますけれども、特に県ゴルフ協会からは、本年1月から11月の間、まだ1カ月残っていますけれど、韓国を中心に約2万1千人の方が愛媛県のゴルフ場に来県されておりまして、東予や南予のゴルフ場にも利用者が徐々に増えてきているというふうに報告が入っております。今後、厳しい寒さでゴルフ環境が整わない韓国からの利用者は、愛媛は年がら年中365日プレー可能でございますので、さらに順調にいくんではないかと期待の声が上がっております。
こうした中、県では、増便後の持続的な安定運航につなげるため、インバウンド・アウトバウンド両面から、新規顧客やリピーターの獲得に向け、プロモーションをはじめさまざまな利用促進策を展開しております。
まず、インバウンドについては、現地メディアやインフルエンサー、旅行会社等を招請し、SNSや多様な媒体を活用した情報発信による本県の認知度向上それから旅行商品の造成による誘客、県内全域の周遊促進等に取り組んでおります。
これに加えて、韓国向けには、ゴルフ需要のさらなる喚起はもとより、東予の新たな周遊ルートの創設に向けて、バスツアーによる実証実験を2月に実施する予定でございます。また来県者に人気のラーメンマップ等に加えて、韓国人の関心が高いカフェやパンの食べ歩きマップも現在作成中でございます。
また、台湾向けも今回新たにゴルフツアーを組み込んだ旅行商品を造成いたしまして、これやっぱり同じように好評でございます。そしてまたもう一つ、台湾の方が特に関心・興味を持つスキー場のPRにも、他の本格的なスキー場と違って、本当にこれは珍しいと思いますけど、今日はゴルフ、明日はスキーなどいろんな組み合わせができるコンテンツの中に1日日帰りで行けるスキー場というのが強みだと思いますので、このPRにも注力しております。
加えて、年明け2月には、昨年度大変盛況であった「大愛媛フェア」、これを台北市中心部で再び開催し、さらなる誘客拡大につなげていきたいと思っています。
空港もコロナ禍にスポットの増設と国際線ターミナルの建設に取り組んで、いいタイミングで5類移行になりましたので、順調に来てくれていますから、リピーターにするためには各市町の取り組み、受け入れ態勢の整備も重要になってまいりますので、また市長会や町村会を通じて各地域にも協力をお願いし、それぞれの地域の活性化につなげていただけたら幸いに思っております。
またアウトバウンドについては、年末年始から春にかけての旅行需要のさらなる掘り起こしを図るため、秋以降、県内はもとより、高知県や香川県へ向けても、テレビCMやタウン情報誌、そして市内中心部での街頭ビジョンなど複数のメディアを活用した路線PRを集中的に展開しております。
そして、もう一方は便数が増えてくるとビジネスでの利用が便宜を増してまいりますので、この獲得に向けて、県内企業や団体へ県の職員が直接出向いて、松山空港国際線の利便性を周知しているほか、若年者の利用促進に向けて、県内の大学と連携しまして、海外旅行セミナーの開催、また新たに大学祭でのブース出展を行ったところでございます。県内企業や学生から高い関心が示されているなど、今後の利用促進につながる種まきができてきているんではないかと思ってます。
さらに、アジア有数のハブ空港となっておりますソウル・仁川空港からタイ、フィリピンへの乗り継ぎ利用の促進にも注力すべく、航空会社に交渉をしておりました。その結果、先日から、松山空港発着のバンコク、セブ、バリ行きの旅行商品の販売が開始されましたので、本当に手頃なリーズナブルな価格でパッと行けますので、ぜひ多くの県民の皆様にご利用いただきたいというふうに思います。
今後とも、航空会社や旅行会社等と連携し、市場ごとのターゲットに応じたニーズを把握して、ただ単に路線を引っ張ってくるというのではなくて、マーケティングを行った上で、戦略を組み立てた上で、認知度向上や観光・ビジネス需要等の喚起に向けて取り組みを進め、国際線のさらなる利用促進を図るとともに、民間の試算では、この段階で年間108億円の経済効果があるというふうなことでございますので、県内各地へ波及できるよう、事業者、市町、DMO等と一丸となって多様な施策を展開していきたいと思ってます。以上です。
(愛媛新聞(幹事社))
ただいまの答弁に関して、質問のある社はお願いします。
(愛媛新聞)
愛媛新聞です。韓国に関してなんですけども、非常戒厳の影響で、韓国の政局が不安定になっていて、韓国への旅行のキャンセルが出ているという報道もあるかと思うんですけれども、松山便の利用によるアウトバウンド、松山から韓国への旅行者に対する影響がどの程度出ているという状況でしょうか。
(知事)
インバウンドについては、そう大きな影響はないというふうに航空会社から連絡が入っております。日本の場合も、どうしても、私も商社にいたんですけども、例えば、当時思い起こすのが、ちょうど勤務していた時が、イラン・イラク戦争の最中でありました。時折事件が起こることがあったんですけども、日本の報道を見ますと、その一つの事案が毎日起こっているような報道になってしまうので、これがやっぱり島国の情報キャッチの限界というものなのかなとういことを当時感じたことがあります。
通常、イラン・イラク戦争の時でも駐在員は現地にいましたし、普通どおり日常生活も送られていましたし、ビジネスも何ら影響なく、緊張感はありましたけども、進められていたという経験がありますので、別に今、韓国行ったら危ないとかそういう状況ではありませんから、その辺は、冷静に受け止めるのもこれから国際社会がどんどん進んでいく中で、そういう貴重な体験にもつながるんじゃないかなというふうに思います。
もちろん、なんていうんですかね、クーデターが起こるとか、そういうときは別ですよ。でも民主国家の韓国の中で、政権交代とか政局などがイコール一般旅行や社会の危険性が極端にアップするとかそういうものではないというふうに思っています。
(愛媛新聞)
少なくとも今は、そういう状況にはないと。
(知事)
そうですね、はい。
(愛媛新聞)
ありがとうございます。
(愛媛新聞(幹事社))
ほかにありますか。
(テレビ愛媛)
先ほど、仁川経由の海外への乗り継ぎ便というのが、旅行商品が販売開始されたということですけど、愛媛が中四国で海外への旅行に出る際のハブとしてのなにか役割として期待されるものというのはありますでしょうか。
(知事)
これは他の地域も今、地方空港を抱えている全ての都道府県が直行便の誘致に取り組んでいるんで、どこがということではない段階だと思っています。それぞれの県でポテンシャルを生かして、どこまでできるかという挑戦をしている段階だと思いますので、ただ単に便数を増やしていくということになると、例えば、受け入れの宿泊のキャパであるとか、あるいはグランドハンドリングとか、いろんな問題がひずみとして生じてきますので、じっくりと構えておくというのがすごく大事だと思ってますので、しっかりとした既定路線の成熟度を高めるということと、それから可能性がある新たな路線がもしあるならば、そこに戦略的に取り組むという愛媛県のあくまでも立場に立った活用というものを中心に、今は考えている段階だと思ってます。
(テレビ愛媛)
グラハンの関係もあると思いますが、新たな路線の可能性、なにか今考えてらっしゃることはありますか。
(知事)
常に考えています。常に。
そういった面においても、まだ全然結論が出ていないですけれども、将来そういったことも踏まえた上での空港のあり方を検討するというのは、こうしたことの変動要因も含めてやっていく時期に来ているかなということで、いろんな方々の知恵を借りている段階でございます。
(テレビ愛媛)
一点、空港に関しては、先日もビジョンの検討中間報告があったと思いますけど、 現在の空港の課題というのはどういったものがあると思いますか。
(知事)
いろんな課題があると思います。将来見通しであるとか、それからそれに近づくための路線の戦略であるとか、それから運営体制であるとか、それから今言った受け入れの、特に今、人口減少が起こってくる日本の国においてあらゆる業界が人手不足に陥っている。特に安全を管理するこうした交通機関においては、人の確保ができなければ安全面がおろそかになるという根本的な問題がありますから、そこを十分に見込んで、じゃあその将来不足するであろう人材をどうやって確保するかとか、いろんな課題を今、多方面から議論していただいてますので、民間の知恵も借りながらやらないと、とてもじゃないけど結論が出ないと思いますから、そういった中での議論の結果を踏まえて、その後は速やかに対応していきたいなというふうに思ってます。
(南海放送)
運休が続いている上海線についてお伺いしたいんですけれども、知事が課題に掲げていた双方の入国のビザが緩和されるというような一部報道もあります。再開の見通しであるとか、航空会社との交渉の進捗についてお伺いできればと思います。
(知事)
これも商社時代に学んだことなんですけれども、交渉事というのはいろんな変化によって、良い局面もあれば、厳しい局面になることもあると、場合によっては途切れるということもあると。だた、その途切れた場合でも将来の再開へのビジネス取引の再開に1パーセントでも可能性があるならば、パイプは絶対切らしてはいけないという教えを叩き込まれた経緯があるので、上海便についてもコロナで、あるいはビザの問題も含めて、いろんな課題があった中で、特にこだわったのは、ビザの関係で、これまでは大阪へ行って、いろんな情報を書き込むという作業が取得のために必要でしたから、それはちょっとどうなのかなというふうに思っていましたので、これが双方緩和されていくということであるならば、さらに1パーセントから2パーセントへ3パーセントへと可能性が拡大していきますんで、その拡大に従って、交渉を進めるスピードも上げていくといふうな段階に入ってきたと思っております。
(あいテレビ)
全国的にはですね、オーバーツーリズムなどの問題も出てきている中で、インバウンド需要が盛んな中において、自治体独自の宿泊税を導入するところも出てきてますが、都道府県でも結構増えてきてると思うんですけども、愛媛県として宿泊税についてはどういうふうにお考えかっていうのをちょっと教えていただければと。
(知事)
もちろん可能性がゼロとは言いませんけども、別によそがやったからすぐやろうという考えは今の段階ではありません。
冷静に業界の意向も見極めなければいけませんし、それから物事って良いときもあれば悪いときも山あり谷ありだと思うんですけども、このインバウンド需要というものが、ただ単にブームで上乗せされている部分もある。
それから大事なのはコアなファンをしっかりと捕まえて、リピーターも含めて将来的に安定した行き来を確保するという戦略もある。両方あると思うんですね。愛媛はどちらかっていうと、後者に力点を置いているんですけども、今円安ですし、全国すべての地方空港が直行便誘致に奔走していますから、アクセスは良くなったんだけど、今の世界的な経済情勢とか円安の動向であるとか、こういったものも大きな要因として後押ししていると思うんですね。
それから、これが山あり谷ありの話でいくと、どうなっていくか誰も見通しがつかないと。だから、焦らずに、それから背伸びしすぎないようにということが大事なのかなというふうに思っていますので、本当に冷静に考えていきたいなというふうに思っています。
(愛媛新聞(幹事社))
各社さん他よろしいでしょうか。それでは代表質問以外で質問のある社はお願いします。
(愛媛新聞)
四国中央市で建設計画が進んでいた新中核病院について運営事業者が計画を一時中断すると発表しましたが、経営環境悪化のため、病床数や病院規模を再検討するとのことですが、統合予定の三島医療センターはもともと県立病院だったということも踏まえて現状どう捉えているか、また、県として何かサポートを考えているかなど、知事のお考えをお聞かせください。
(知事)
四国中央病院の新築整備事業については、今、安定的な医師の確保が非常に難しい状況が続いていること、それから物価や人件費が御案内のとおり、ここへきて急騰しているということ、また、これ公立病院全てが抱えていますけども、コロナ後に患者の回復が思ったように進んでいないということ、ほとんど全ての全国の病院で、非常に厳しい経営環境が続いている状況でございます。その結果、今月から開始予定であった、これ病院自体は平成10年から閉まっているのかな、ごめんなさいね。平成じゃなくて、令和元年から閉じてるんで、6年間閉鎖状況が続いています。そういう中で、コロナも含めてやりくりはしてきた状況にあります。そういう中で、今月から開始予定だった三島医療センターの解体工事を含む全ての事業を一時中断、一時中断して、改めて病院規模など事業の実施について検証することとし、まず現病院の経営改善に向けた現状把握をあちらの方で行っているというふうに話がありました。
県では宇摩医療圏の医療提供体制を確保するため、地域枠の医師、奨学金等々のバックアップをして県内に9年間残っていただくという制度でございますけども、こういった医師の配置、それから、新病院建設費用の補助、これを通じて四国中央病院を支援してきたところでございます。
今回の組合の発表は、新病院の建設を望む地元の方々にとって大変気がかりなものと理解しておりますが、現時点では、現時点ですあくまでも、新病院の開院時期については、令和10年度開院の目標は変更しないとされておりますので、今後の状況を注視していきたいというふうに思います。
また、組合の方でこれ詳細は分かりませんけれども、地元の四国中央市に対しても、財政支援等を要請しているということでございますんで、市とも情報共有を図りながら、将来にわたり地域の医療を安定的に提供できる体制の確保には引き続き取り組んでいきたいというふうに思います。以上です。
(毎日新聞)
すいません。毎日新聞です。国のエネルギー政策の指針となる基本計画が、昨日25日に審議会で実質了承を得たんですけども、これまで盛り込まれてた原発の依存度を低減するという表現が削除されて、原発活用を最大限に進める方針が示されていますが、県内には伊方原発もあると思うんですが、知事としての受け止めをお願いします。
(知事)
はい。今回示された原案というのは、刻一刻、変化していく国際情勢の動向、あるいは現行計画の策定以降における社会経済全般の状況、これを踏まえて、エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素を同時に実現していくということが大きなテーマとされておりますが、ご案内のとおり日本は四方を海に囲まれていて、自前のエネルギー資源をほとんど持たない、資源が非常に乏しい。これはもう日本の弱点でもあり、宿命でもあり、常に対策が求められる分野でもあるというふうに思います。そういう中で、エネルギーの安定供給と安全保障の問題は極めて重要でありますから、これはエネルギー政策というのは国がつかさどりますんで、全体の国としての計画、しっかりと議論を進めてほしいと願っております。
また、お話のあった原子力発電については、電源構成に占める割合は、現行計画と同水準とされておりますが、再生可能エネルギーとともに、エネルギー安全保障に寄与し脱炭素効果の高い電源として、可能な限り活用する旨が示されております。先ほど、お話したとおり、エネルギー政策というのは国策であり、国が責任を持って議論すべきものでありますことから、このことについて県として何か、是非というものについてお答えするつもりはございませんけれども、運転期間の延長、次世代革新炉へのリプレースなどの議論のみが先行されることのないよう、問題点というのはもういろいろと出てきてますから、最終処分の問題、こういったことを始めとして、核燃料サイクルや廃炉などのバックエンドプロセスの議論、これをやっぱり並行して着実に進めることが肝要だと思いますので、このことについては、原発立地県として常に申し上げてきたところでございますので、しっかりと対応していただきたいと願ってます。以上です。
(NHK)
NHKです。戦後80年の取り組みについてお伺いします。来年2025年は戦後80年でありますけれども、そういった中で、次の世代に向けて戦争の体験だとか、また、先日、中村知事は、被団協の松浦さんと面会されましたけれども、被爆者の思いだとか、証言っていうのをどう伝えていくおつもりかという、その取り組みについてお伺いできますでしょうか。
(知事)
そうですね。松浦さんとの話の中でも触れさせていただいたんですけども、僕自身も幼少期に祖父の影響で、何回か広島の原爆資料館(平和記念資料館)、あるいは江田島、そして知覧(特攻平和会館)等々、どちらかというと連れて行かれて歴史を学べというふうな経験がありました。子供心に、本当に戦争の恐ろしさ、悲惨さというものが、その体験を通じて、心に刻まれたように思います。
幼少期の怖さというものが、戦争は駄目だっていう強い思いに結び付くと思うので、歴史を振り返るということは、非常に大事な視点ではないかなと思います。
ただ、今もう戦後数十年を経て、戦争を知らない世代が大半を占めるようになりましたので、現実感というものが社会全体に失われつつあるということは、非常に心配をしています。
かつて商社にいたときに、実際に紛争をやっている国との取引等も行っておりましたので、日本はずっと戦後、幸いなことに平和社会が続いていますけれども、今この時点でも、ロシアとウクライナ、あるいはイスラエル等々の問題、そこら中で紛争が続いています。
だから、平和というのは当たり前ではなく、みんなが考え、努力して勝ち取っていくもの、掴み(つかみ)取っていくものなのだっていうことを伝えていく必要性、重要性は、逆に、戦後世代が中心になってきているが故に、より大切になってきているんじゃないかなというふうに思います。
ですから、被団協の核兵器廃絶に向けた地道な活動は、心から敬意を表させていただきたいと思いますし、そういう環境を受けて、今回のノーベル平和賞につながったんではないかなというふうに思っています。
愛媛県でも、毎年の戦没者追悼式であるとか、さまざまな行事へのバックアップを行っておりますけども、さらに、紫電改の展示館についても、これは単に紫電改という昔の飛行機を引っ張り上げたというだけの意味では全くなくて、あの時代に何があったのか、こんなことがあったんだ、こんなものが造られていたんだ、こんな悲惨な背景があったんだというようなことを感じ取れるような、展示館にできればよいのではないかというふうに思いますので、しっかりと継承をしていきたいというふうに思っています。
(NHK)
戦争を体験した愛媛県内の世代に聞くとですね、証言を活動しているけれども、人もお金も足りないと、行政のバックアップもなかなか不足してるんじゃないかっていう声もあります。そういった中で、行政としてそういった団体だとか、人たちをどうフォローしていくのかということもお伺いできればと思います。
(知事)
この段階でどうだっていうのはちょっと把握もできてないんですけど、例えば私も松山市の仕事をしていましたけど、基礎自治体単位でいろんなことやっていますので、そこらあたりの動向なども確認した上で考えていく必要があるんじゃないかなと思っています。
(NHK)
あと一点だけすみません。被爆地の広島ではですね、被爆伝承者の養成制度、被爆した方々の証言を若い世代が引き継いでそれを伝えるっていう制度、事業もあるかと思います。県内にも被爆者がいますけれども、そういった伝承の活動というところに取り組んでいくお考えはあるのか。また、広島のその制度に、何らかの形で関与していくだとか、そういったお考えというのはいかがでしょうか。
(知事)
広島と長崎については、実際に原子爆弾が投下されて焦土と化した、大勢の市民が一斉に亡くなったという、(愛媛とは)全く状況が違うので、それと同じことというようなことでは、ちょっと取り組みは難しいかなと。
そういった資料館への、小学校、中学校時代の修学旅行とかは非常に意味があるんじゃないかなと思うので、そこでの連携とかを通じて呼び掛けていったらいいんじゃないかと。これも強制はできないんですけども、あくまでも学校、生徒等が決めていく組み立てですから、その選択肢の中にこういうことがあるよということを、常に紹介していくということは重要だと思っています。
(愛媛新聞)
愛媛新聞です。よろしくお願いします。
緑町の土砂災害について伺います。先日、4回目の県の対策技術検討委員会が終わりましたけれども、発生のメカニズムについては、概ね解析できたのかなという点と、対策工事も示されたかと思います。改めて進捗状況を知事としての受け止めをお聞かせください。
(知事)
そうですね、やはり災害規模の大きさと、それから犠牲者の方が3名亡くなっているという重み、こういったことがあるので、本当に公平なメンバーによって分析をするということが非常に重要だというふうに発生当時考えました。そうなると、やはり地元の方だけではなく、国の、やはり専門的な知識を持った方に参加をいただいて、検討していただくことが重要ではないかということで、これは市のレベルではなかなか難しいのではないかなと判断しまして、検討委員会の分析については県の方で声掛けをさせていただきました。その結果、国の方からも参加をいただいて、公平に分析が進められたと思います。もちろん自然災害でありますから、100パーセント解析するのは、これは人間の力では難しいと思いますけれども、大まかなメカニズムの解析はしていただけたのではないかなと、この前の報告を聞いて感じました。
それによると、土砂災害発生の要因としては四つあると。一つは降雨、水量ですね。それからもう一つが、樹木の成長で負荷がかかったと。それから、道路の工事によっての荷重の増加、これが擁壁を置いたことによって、やっぱり荷重が増加していると。それから元々盛土もありましたので、その捨土。昔、お城を作ったときの捨土ですね。この斜面の侵食作用、この四つが原因というふうに見られるということが、メカニズムとして特定されました。その結果、この四つの要因が複雑に絡み合いながら、土壌が緩み、ここはわからないんですけれども、中腹ないしは上部から、どちらかから崩れたのだろうという推測が、可能性というものが示されたというふうに受け止めています。
こうしたことで、できる限界はあるけれども、非常に第三者による分析というものがしっかり行われたということで、ある程度、最終的には1月末を目途にということになっていますけれども、この段階で大まかな解析は完了したのではないかなというふうに捉えています。
(愛媛新聞)
大まかな解析が進んだ中で、一方で松山市の方が、市による市民に対する説明会というのがまだ実施されていないかと思います。先日の委員会後、市長の記者会見でも、「従来通り委員会の結論がしっかり出た上で検討する。」という答弁もありましたけれども、概ね、大まかな解析が終わった今の段階でも説明できる部分はあるのではないのかなと思いますが、改めてそのあたりの知事のお考えというのはいかがでしょうか。
(知事)
これは道路、城山を管理していた市が決定することなので、何て言うんですかね、感想とかアドバイスしかできないんですけれども、先ほどの鳥インフルと同じように、大きな災害が起こったときは、寄り添うということがすごく大事だと思います。いろんな厳しい声もあると思うんですけれども、でもそこを経ることによって、できること、できないこと、冷静な話し合いが進められていくと。西日本豪雨災害の時もそうでしたので。別に道路の問題、解析の問題とか、その他にもいろんな課題があると思うので、僕は個人的には、やっぱり説明はもう一刻も早くやられた方がいいんじゃないかなというふうに思います。県と市との(連絡)調整会でも、担当者の方から繰り返し「やられた方がいいんじゃないですか。」ということは申し上げてきたんですが、最終的な判断は松山市になりますので、延ばしているということの意味はちょっと私はよく分からないです。
(愛媛新聞)
ありがとうございます。
(あいテレビ)
すいません。あいテレビです。原発関連でちょっとお伺いしたいんですけれども、来年度から中国電力が原発に関わる島根県と周辺自治体の人件費を年間5億円ぐらい負担するというような、この前取り決めがなされたということなんですけれども、同じ原発立地県の知事として、一定、これ合理性があるかなとも思うんですけれども、原発に関わる自治体の人件費を電力が負担するということについてはどうお考えでしょうか。
(知事)
ちょっと。その情報、僕、細かく聞いてないんで、ちょっとこの場で間違ったこと言えないんで、非常に重要な話ですから、ちょっとここではご容赦いただきたいと思います。すいません。あの情報ちょっと入ってないんで。
※会見翌日(27日)に以下のとおり記者クラブに回答
報道によると、島根県では、5年ごとに行われる核燃料税の更新に関する協議において、税率を17パーセント相当で維持し、県職員等の人件費については、中国電力が年5億円を別途負担することで合意したとのことであるが、両者の協議内容の詳細は承知していない。
本県においては、令和6年1月の更新の際に、今後5年間で見込まれる財政需要について、県職員の人件費も含めて算定したうえで、四国電力と更新協議を行い、税率を17パーセント相当から18パーセント相当に引き上げたところであり、税率を据え置いた島根県とは状況が異なる。
(時事通信)
時事通信です。知事が有識者として参加している地方創生の会議についてお尋ねします。
今、国では、新しい地方経済・生活環境創生会議というものが立ち上げられて、中村知事も有識者として参加されておられます。24日に基本的な方針というものが国の方で取りまとめられたかと思います。中村知事も有識者として参加して意見も特に舌鋒(ぜっぽう)鋭く述べられた部分もあったのかなと思うんですけども、地方の意見、現場の意見というものが基本方針にどれぐらい反映されているのか、改めて、この後、会議も続きますけども、どのように会議に臨んでいくか教えてください。
(知事)
(会議に)参加されたメンバーは、多種多彩だと思います。ただ、地方の現場を知っているメンバーは、本当に少ないですね。だから皆さんいろんな視点で発言されますから、そういったたものも非常に新しい刺激としていいんではないかなと思いますけれども、あまりにも現場とかけ離れてしまうと実効性が伴わないということで、現場視点で主張するというのが自分の大きな役割だと思っています。例えば、こんな話があったんですね。
ある委員さんから、そもそも市町の単位をすべて見直すべきだというような意見が出たことがありましたけれども、僕がそれは待ってくれと。今までの歴史があるんですと。地方分権論議から三位一体改革、それから市町村合併で乗り越えて。ある意味では、3300の自治体が1800まで削減されて、議員さんはみんな失業していったと、そのリストラを乗り越えて今があると。地方公務員もその間で7パーセント近く減少、一方で分権で仕事が減った国家公務員は2.5パーセントしか減っていない。こういう実態を知らないで、市町村に市町村合併をもう1回やれと言ったら、大変なことになりますよと。ああそうだったんだっていうような議論もあるんですよ。
よほど性根を据えてやらないといけないなと思っているんですけど、私の方から今の段階で言っているのは、一つはナショナルミニマムの問題ですね。先般、長谷川議員も参加されている自民党の会が政府に対して要請されていましたけれども、前々から申し上げているとおり、地方自治体で競争になってしまっている子どもの医療費の問題、学校給食の問題、保育料の問題、交付金を出しても一時的にそれに使っちゃえということにもなりかねないと、だから交付金を増やしても本当に意味のある交付金につながらない可能性もあるし、ここをリセットして国がやるべきこととして位置付けて、無用な競争が地方自治体間でばらまきのところで行われないように、リセットする必要ありと、それがあって初めて、地方創生に本腰を入れられるんじゃないかっていうのがまず1点です。それからもう1点は、そもそも地方自治体がスキルアップしなければ、交付金が増えても使いこなせない、使いこなせない自治体では、最終手段として期限が来ると、商品券、地域版協力金、これに消えていくだけで一過性の政策しか出せない。だから、やはり将来の成長の糧になる事業を見極めて、そこを徹底的に後押しするという運用の仕方というのは、やっぱり考える必要があるし、本来は、その実力を地方が、県も市町も含めて備えなければならないけれども、まだ途上です、だからそれを前提にKPIなんかを駆使しながらやっていく必要があるんじゃないかと。もう1点は、地方創生の事業というのは、ほとんどがデジタルの技術を使うことが多いんですね。ところが国は、地方創生交付金とデジタル交付金があるんですよね。われわれからすれば、どっちでもいいんだけれども、国の組織上ですね、ここの連携が全くないんですよ。完全にセパレートしています。片やデジタル庁、片や内閣府、これがそもそも体制としておかしいんじゃないかということで、国の側の組織の問題をやる必要があると。最後に四つ目が、東京の大手企業というのは、非常に今、収益を上げて蓄積されていると、その収益が、その結果として、時折、企業版ふるさと納税で地方にという声も来ています。ただ、企業側としては、今年は利益が出たから、その余剰分で企業版ふるさと納税やろうねという段階ですと、ここに企業側に基金を設けて、そこに利益が出たときは積んで、活用するときに損金処理ができるような税制上の仕組みを作り上げれば、企業も長期的な視点に立ったふるさと振興、これが可能になるということで、財務省はたぶん猛反対すると思いますけれども、地方創生という観点からは、大手企業の蓄積された収益が東京に落ちるだけではなくて、地方の創生にもいざなえるという道筋をつけるという意味で必要ではないかという主張をしています。そんな地方の現場から、体験からにじみ出た意味のある提言を、採用されるかどうかは分かりません、なんせ絶対的な人数が少ないです、少数派ですから、でもそこはその分を大きな声でカバーしていきたいと考えています。
(共同通信)
共同通信です。昨日、伊予鉄バスさんが全国で初めて自動運転レベル4で路線バスの本格運行を始めました。人手不足や人口減でですね、バス路線の廃止なども問題になる中、こうした自動運転の動きがあることについての受止めであったり、期待する部分があれば教えてください。
(知事)
ある意味では最新のテクノロジーを活用して、日本で初めてレベル4の自動運転にトライするということで非常に注目をしております。これは国の実証実験、国の方が費用もサポートするということでスタートできたと思いますけれども、そもそもですね、AIを活用した自動運転、本当に、レベルを上げていく事によって誰もが不安に感じるのは、事故大丈夫なのかな、あるいは、事故が起こったときの補償とかどうなるのかなとか、あるいは自動運転技術を悪用されると、例えばテロ攻撃に使われたり、そういうことの懸念もある。だから、なかなか難しい課題がまだまだあると思うので、その中で、今の範囲でレベル4までは何とか限られた空間であればいけるんじゃないかということでの実証実験は非常に意味があると思ってます。
ただ一方で、ここは本当に分からないんだけど、一番安全に自動運転ができるとすれば、僕は鉄道だと思うんですよね。だって、車両が入ってくることもないですし、踏切は別としてね。本当に閉ざされた空間をレールの上を走るということで、これこそ自動運転に一番向いてそうなのに、あえて難しい方から入っていくっていうのが、ちょっと個人的には同時並行ぐらいでやったらいいのにな、というふうな感想は持っていますね。
(愛媛新聞社)
愛媛新聞社ですが、先日、愛媛大学工学部に建築学が学べるコースが新設されることが発表されました。1級建築士の受験資格に対応しており、同様の大学がないのは四国では現在愛媛だけで、県も県内の業界と一緒になって、技術系人材の確保や、あるいは県内の高校生の地元進学の選択肢を広げる観点から、大学側にコースの創設をお願いしていたというふうに聞いております。
2年後の開設後にはですね、県も技術系の職員を講師役として派遣するといった協力なんかも検討していると聞いているんですが、知事の期待感をお聞かせください。
(知事)
はい、あの非常に期待しています。というのは民間投資が盛んな状況の中で、地方自治体における技術職の確保は本当に難航してます。一般行政職は、県、かなり受けていただけるんですけども、土木技師等々技術職員は、毎年定員割れが続いてます。
そこで期間をずらして採用を、民間採用から、それからこの前も延長してもう1回やりますっていうことをやらせていただきましたけども、確保するために本当に年がら年中探し回ってるという状況なんですね。
そういう状況もあったので、大学に対して人材育成のコース、これ実は建設業協会も同じ悩みを抱えてますから、あることによって人材確保に絶対につながると信じてますと、いうことで依頼していた経緯はあります。それを受け止めて、地域に根ざした地域に貢献する大学という視点からやりましょう、というご返事をいただきましたので、本当に感謝してます。出していただくからには、県の職員の派遣も含めて、全面的な協力をしていきたいな、というふうに思ってます。それを、県職員の技師の確保に、ぜひとも結び付けていきたいと思ってます。
※議事録については、読みやすさや分かりやすさを考慮し、発言の趣旨等を損なわない程度に整理しております。