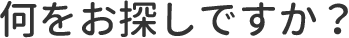本文
愛媛県人権施策推進基本方針(第四次改訂)の策定について
当基本方針は、本県の人権施策の総合的な推進を図るため、愛媛県人権尊重の社会づくり条例(平成13年4月施行)の規定に基づき、平成16年12月に策定し、その後、平成27年3月に第二次改訂版、令和2年3月に第三次改訂を策定しました。
このたび、人権を取り巻く社会情勢の変化や新たに発生する人権課題への対応等を踏まえて、愛媛県人権施策基本方針(第四次改訂版)を策定しました。
- 愛媛県人権施策推進基本方針(第四次改訂)全文 [PDFファイル/2.72MB]
- 愛媛県人権施策推進基本方針(第四次改訂版)の概要 [PDFファイル/293KB]
- 愛媛県人権施策推進基本方針(第四次改訂版)の構成 [PDFファイル/141KB]
基本理念
人権という普遍的な文化の創造
この基本方針は、県民一人ひとりが互いに人間の尊厳や権利を尊び、差別や偏見のない地域社会の実現を目指して制定した「愛媛県人権尊重の社会づくり条例」第5条の規定に基づき策定するものです。そして、県民自らが、人権尊重の社会づくりの担い手であるという認識のもとに、県や市町、NPO、各種団体など地域で活動する多様な主体同士が協働して、人権意識の高揚や人権擁護に係る取組を進めていくための基本的な考え方を示すものです。
また、「人権教育のための国連10年」愛媛県行動計画を引き継ぎ、「人権という普遍的な文化」の創造を基本理念に、人権教育・啓発や人権擁護を総合的に推進するためのものです。
この基本方針は、他の様々な施策に関する計画や方針の策定にあたって、準拠すべき基本指針としての性格を有するもので、県が推進するあらゆる行政の分野で、人権尊重の理念を浸透させていくものです。
基本方針の目指すもの
子どもから高齢者まで県民一人ひとりが生活に生きがいを感じ、安心して暮らすことができる「愛顔あふれる愛媛県」の実現を目指す。
3つのキーワード
自己実現を尊重する(全ての人が自分らしい生き方のできる地域社会の実現)
人権が尊重される社会の実現のためには、一人ひとりの様々な生き方の可能性が否定されることなく、その人本来のありのままの個性や能力を十分発揮できる機会の保障が重要です。お互いの自己実現を尊重していくためには、相手の立場に立って考え、行動することが求められており、すべての人が自分らしい生き方のできる、お互いの自己実現を尊重する地域社会の実現を目指します。
共同参画を保障する(全ての人が平等に参加できる地域社会の実現)
人権が尊重される社会の実現のためには、性別や年齢、障がいなどによって制約を受けることなく、誰もが地域社会の構成員として、あらゆる分野への参画が保障されることが重要です。特に、政策決定の場に当事者が参加し、意見を表明できる機会が保障されることが求められており、すべての人が平等に参加できる地域社会の実現を目指します。
共生社会を目指す(全ての人が安心して暮らすことができる地域社会の実現)
人権が尊重される社会の実現のためには、すべての人が、それぞれの多様な文化や価値観を尊重し、それぞれの個性や生き方の違いを認め合い、自らのこととして考え、共に生きているという認識や他人を思いやる心を持つことが大切です。
ユニバーサルデザイン*の考え方にのっとり、また、SDGsの取組に対応してすべての人が障がいの有無、性別や国籍の違い、年齢などに関係なく、安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指します。
1 人権教育・啓発の推進
(1)あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進
人権意識を高めるため、人権の意義やその重要性が知識として身に付くよう啓発を行うことはもちろん、日常生活の中で人権への配慮が行動や態度に現れるよう、家庭や学校、地域社会、職場などあらゆる場を通じて、人権教育・啓発を推進します。
とりわけ、人権感覚は一朝一夕には身に付くものではないことから、様々な人権問題について、生涯にわたり継続した学習ができるよう、子どもから大人まで、長期的な視点に立ち、認識不足や思い込みによる無自覚な言動によって他者を傷つけることのないよう留意しながら、当事者意識を持った対応ができるよう、より実践的な学習活動を進めていきます。
(2)特定の職業に従事する者に対する人権教育の推進
人権尊重の社会づくりを推進していくためには、県民一人ひとりが人権問題に対する正しい理解と認識を深めるとともに、人権感覚を磨くことが重要であり、あらゆる場を通じた人権教育を推進していくこととしています。とりわけ、公務員、教職員、警察職員、消防職員、保健・医療・福祉関係者、マスメディア関係者は、日頃から人権の擁護に深い関わりを持つ職業に従事しており、その職務の性質上、人権に配慮することが求められています。
これら特定の職業に従事する者への人権教育は、これまでも各機関や各職場において、それぞれ行われてきたところですが、今後とも人権尊重の理念の浸透が図られ、効果的な人権教育が行われるよう積極的な支援に努めます。
(3)指導者等人材育成の推進
県民が日常生活の中で、人権に配慮した行動がとれるよう人権意識を高めていくためには、身近な学習の場において、様々な人との交流やふれあいを通じて、人権教育に広く参加できるよう環境を整えるとともに、人権教育・啓発に携わる指導者の養成が重要となります。
このため、愛媛県人権啓発センターでは、企業における公正採用選考人権啓発推進員や市町担当者、教職員、保健・医療・福祉関係者などを対象にした研修や情報の提供を行い、日常生活の中で主体的に人権教育・啓発の推進が図られるよう、人材の育成に努めます。
重要課題への対応
1 女性
2 子ども
3 高齢者
4 障がいのある人
5 同和問題
6 外国人
7 エイズ患者・HIV感染者・新たな感染症(新型コロナウイルス感染症等)
8 ハンセン病患者・回復者及びその家族
9 犯罪被害者等
10 性的指向・ジェンダーアイデンティティ(SOGI)
11 インターネットによる人権侵害
12 北朝鮮による拉致問題
13 被災者
14 その他の重要課題
(1)刑を終えて出所した人
(2)アイヌの人々
(3)ホームレス・生活困窮者
(4)人身取引
(5)ハラスメント
(6)その他
1 県の推進体制
県が行うすべての業務について、人権に関わりのない仕事はなく、職員一人ひとりが人権尊重の視点に立った行政を推進していくことが求められています。このため、県のあらゆる行政分野で、人権尊重の理念を基礎とした取組を積極的に推進します。
(1)全庁的な推進組織の構築
「愛媛県人権施策推進基本方針」に基づき、人権施策を推進するため、愛媛県人権施策推進本部を設置し、関係部局相互の連携・協力のもと、総合的かつ効果的な施策の推進に努めるとともに、愛媛県人権施策推進協議会の意見や提言を踏まえ、基本方針の適切な進行管理に努めます。
(2)愛媛県人権啓発センターの機能強化
人権啓発活動の拠点として、2003(平成15)年に県庁人権対策課内に愛媛県人権啓発センターを設置し、人権の総合的な窓口として相談業務や調査研究を行うほか、指導者等の人材の養成、研修手法の検討や講師の派遣・紹介など、人権教育・啓発を推進しています。
今後とも、関係機関、市町、NPO等との連携を図りながら、県民の人権意識の高揚や人権擁護を進める拠点として、人権に係る調査研究や啓発資材の開発、作成など、その機能や組織の充実に努め、人権施策を総合的かつ効果的に推進していきます。
2 国及び市町との連携
人権施策の推進にあたっては、国、県、市町がそれぞれの立場から、様々な取組を行っており、人権尊重の社会づくりを進めていくためには、相互の緊密な連携のもと、協力体制を強化していくことが必要になっています。
このため、法務局や人権擁護委員などの国の機関や市町等と構成する人権啓発活動ネットワーク協議会の連携を強化し、効果的な人権啓発活動を進めていきます。
特に、市町は、県民に最も身近な地方公共団体であり、地域の実情に即したきめの細かい人権啓発活動を行うことにより、より大きな効果が期待されることから、市町に対して、人権教育・啓発に関する情報提供や指導者の育成など、積極的な支援に努めます。
3 NPO、各種団体等多様な主体による協働
人権意識の高揚や人権擁護の推進については、行政だけでなく、NPOや各種団体、企業など地域で活動する多様な主体による協働が不可欠であり、県や市町がこれらの活動との連携を図り、協働して人権が尊重される社会の実現に努めます。
特に、近年、価値観の多様化や地域社会を取り巻く環境の変化に伴い、ボランティア活動やNPOに参画する人が増加し、地域づくりの担い手として、大きな役割を果たすようになっており、第4章で取り上げている多くの人権課題について、様々な活動をしているNPOやボランティア団体があります。
行政としても、これらの自主的な取組やノウハウを活かしていくことは、県民が主体的、自主的な活動により人権教育・啓発を推進する観点からも重要であり、人権啓発活動でのNPО等との連携をはじめ、県民が参加しやすい啓発活動が行えるようNPО等の多様な主体との協働を推進します。
4 県民に期待される役割
人権が尊重される社会づくりの実現のためには、県民自らがその担い手であることを認識し、人権意識の高揚に努めることが重要です。
すべての人は平等であり、人権はすべての人に保障されていますが、人間は一人ひとり違っており、お互いを認め合い、尊重することができるよう、人権意識を高め、日常生活の行動に根付かせていかなければなりません。
このように、人権問題はまさに、一人ひとりの心の問題であると言え、生涯を通じて、常に学習していく姿勢が求められています。県民一人ひとりの主体的な行動によって、笑顔に満ちた地域社会の実現を目指しましょう。