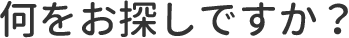本文
試験研究成果
試験研究成果一覧
|
試験研究課題名 |
実施年度 | 実施部署 | 目的 | 主な成果 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漁業資源調査費 | 昭和52~ | 水研センター_環境資源室・栽培研_浅海調査室・東予駐在 | 資源評価対象魚種の資源評価精度を向上させるため、調査船による卵稚仔調査や市場調査等を行い、資源水準及び資源動向の判断等の把握に必要な生物学的情報を整備する。 |
〇調査データは、データ交換システムを通じて水産研究・教育機構水産資源研究所及び水産技術研究所へ報告した。 〇対象魚種の体長組成、成熟状況、性比、肥満度や卵稚仔の分布状況等の生物データ及び標本船日誌、水揚量等の漁獲データを収集した。 |
|
| 漁況海況予報事業費 | 昭和39~ | 水研センター_環境資源室・試験船「よしゅう」 | 本県沿岸域の漁況海況の調査を行い、関係漁業団体や漁業者へ迅速に情報を提供する。 | 〇宇和海、伊予灘、燧灘の海況及び宇和海の漁況について調査し、収集した情報をとりまとめ、関係漁業団体や漁業者に広報した。 | 宇和海海況情報サービス [PDFファイル/414KB] |
| 漁場環境モニタリング調査指導事業費 | 平成12~ | 水研センター_環境資源室・試験船「よしゅう」・栽培研_浅海調査室・東予駐在 |
赤潮等による漁業被害を未然に防止するための水質・底質等漁業環境のモニタリング調査を実施する。 西部瀬戸内海沿岸6県が広域共同調査を行い、有害赤潮の分布拡大域状況を情報化する。 赤潮による被害を防止するため、へい死機構の解明と発生予察を行う。 |
〇調査で得たサンプルを各県と愛媛大学で分析し、水産技術研究所と共同でデータを解析することで、赤潮発生予測方法について検討した。 〇愛媛県沿岸の漁場環境を把握するため、水質・底質・藻場・有害有毒プランクトン等の調査を行った。 |
|
| 資源管理推進事業費 | 平成13~令和8 | 水研センター_環境資源室・栽培研_浅海調査室・東予駐在 | 県内の重要水産資源であるキジハタ、マダイ、ヒラメ、カタクチイワシについて、漁獲・資源動向の把握と、適切な資源管理の確立に努める。 |
〇対象魚種の体長組成、成熟状況、性比、肥満度や卵稚仔の分布状況等の生物データのほか、水揚量等の漁獲データを収集した。 〇カタクチイワシについては、調査データを基に、パッチ網漁の適切な解禁日を決定した。また、今期の不漁原因についての考察を行った。 |
|
| 媛スマ養殖用種苗安定供給事業費 | 令和5~7 | 水研センター_養殖推進室 | 愛育フィッシュの牽引役となる媛スマを周年にわたって販売できるよう種苗生産体制を高度化し、優良種苗の安定供給を図る。 |
〇これまでに得られた知見(ふ化仔魚の安定供給、配合飼料への効率的な餌付け等)を活用した生産システムを運用し、安定的に種苗を生産できた。 〇養殖用種苗111,570尾を生産し、6件の県内養殖業者に出荷した。 |
|
| 媛スマ養殖低コスト・効率化技術開発試験費 | 令和5~7 | 水研センター_養殖推進室 | 収益性の高い新魚種としてスマ養殖の産業化に向けて、種苗代を含めた養殖コストの低減を図るため、種苗生産期・養殖導入期・養殖期の各期に残されたコスト面や品質面の課題解決に取り組むことを目的とする。 | ○種苗生産期の配合餌付け時における光(自然光・緑色)の影響を調べたが、餌付けの成功率や生残率を向上させる効果は確認できなかった。 ○養殖期の飼料について、サイズ別に配合飼料2種(マグロ用・ブリ用)、生餌を使用した飼育試験を実施した。 ○カメラの収差補正と魚影の誤認識除去の改良により、尾数計数の精度が向上するか確認した。その結果、精度誤差5%以内測定結果を得ることができた。 |
|
| 日本一の養殖マサバ産地づくりプロジェクト事業費 | 令和6~8 | 水研センター_養殖推進室 | 日本一の養殖マサバ産地づくりに向け、マサバの完全養殖、ワクチンによる魚病対策、不妊化技術の開発、マサバに適した配合飼料を明らかにすることを目的とする。 | ○通常期(5月)及び非産卵期(2月)に計45,000尾を生産し、完全養殖を達成し、生産種苗を使用して、選抜・養殖試験を実施した。 ○水温別のレンサ球菌症の半数致死濃度を明らかにした。また、不妊化種苗作出に必要な顕微注入技術について、マサバ受精卵で実施可能であることを確認した。 ○タンパク質及び脂質割合の異なる市販飼料を用いて、稚魚期及び成魚期に飼育試験を実施し、それぞれの最適な割合を明らかにした。 |
|
| アコヤガイ異常対策事業費 | 令和5~7 | 水研センター_養殖推進室 | アコヤガイの異常死原因は感染症であることが分かったが、全容解明には至っておらず、いまだ抜本的な対策も確立されていない。そのため、被害軽減対策の検討強化や強い貝づくりを加速化することで、真珠・真珠母貝生産量日本一を奪還する。 | 〇新たな被害軽減対策である陸上飼育について、成長の遅れが課題であったが、培養プランクトンの給餌・飼育水の生海水利用・密度調整により改善された。 〇稚貝・母貝のモニタリング調査を行い、死亡状況、貝の状態を把握するとともに、調査結果を関係者へ周知した。 〇県内種苗生産施設の生産不調に対応するため、緊急生産を実施し、約200万貝の稚貝を配布した。 〇耐病性遺伝子マーカー探索について、新たなゲノム配列データの取得を進めるとともに、コンピュータによるゲノム解析技術の習得に取り組んだ。 |
|
| 真珠母貝仕立技術開発試験費 | 令和4~7 | 水研センター_養殖推進室 | 真珠生産過程におけるアコヤガイの肉質や血液成分の変動について調査し、従来の勘や経験に頼らず、科学的な裏付けに基づき、貝の状態を把握する指標を探索することで、生理的変化を科学的・定量的に明らかにして、真珠養殖業者間で大きな差のあった真珠の製品率と貝の生残率を高いレベルで安定化させ、生産技術の高度化を図る。 |
〇低品質珠の原因となるシミや突起の出現が、X線画像解析等により真珠袋形成に起因する核直上であり、真珠袋の形成を順調にするためには、本事業で開発した母貝とピース貝の相性や、貝リンゲル液の使用が有効なことが分かった。 〇抑制が困難な貝について、肥料として市販されている粒状苦土石灰の利用が有効であることが分かった。 |
|
| 養魚用飼料原料新規開発事業費 | 令和6~8 | 水研センター_養殖推進室 | 輸入原料の高騰による飼料価格の上昇により、魚類養殖業者は厳しい経営を強いられているため、安価な未利用飼料原料を用いた養魚飼料を開発し、飼料コストの削減を図るとともに、循環型の養殖方法への転換を促進する。 |
○複数の昆虫種を原料とする飼料原料について、栄養価の高さと安定供給の体制が構築されている点から、コオロギを選定して試験飼料を作製することとした。 |
|
| 低水温下におけるマダイ低魚粉飼料の成長性改善試験 | 令和5~6 | 水研センター_養殖推進室 | 魚粉価格の高騰への対策及び持続可能な養殖業への転換の観点から、養魚用飼料の低魚粉化を図るため、マダイを対象として、魚粉含量15%の超低魚粉飼料に摂餌を誘引する効果が期待される飼料原料を添加した飼料を作製し、適正な添加量及び給餌量を明らかにする。 | ○カツオペプチド、スパイスミックスの2種に飼料原料の候補を絞り、各原料を添加した飼料を設計・作製して飼育試験を実施した。いずれの飼料でも市販飼料と同等かそれ以上の摂餌率及び増重率を示し、特にカツオペプチドにおいて、より高い効果が得られた。 | |
| 養殖場と凍結精子を活用した育種産物普及システムの開発 | 令和5~9 | 水研センター_養殖推進室 | より大きな母集団から優良な形質を持つ個体を選抜して育種効果を高めるため、養殖場で養殖されているブリの中から有用形質を持つ個体の選抜する方法を検討する。 | ○産卵期前後(12月~翌年6月)の成熟状況調査を実施し、適切な採卵・採精時期を検討した。 | |
| ブリ優良親魚最適組み合わせ選考を目的とした小規模種苗生産技術開発 | 令和5~9 | 水研センター_養殖推進室 | 小規模水槽で安定的に種苗を生産する技術を確立するため、飼育環境及び飼育管理に関する項目について適した条件を検討している。 | ○異なる条件で収容密度、油膜除去方法について比較し、適した条件を検討した。 | |
| 高収益型マハタ養殖システムの開発 | 令和6~8 | 水研センター_養殖推進室 | ハタ科魚類で形態異常への革新的な向上技術が開発されており、この技術をマハタに適用することで生残率と開鰾率の向上を図る。また、ヤイトハタで明らかになってる光による成長促進効果を、マハタに応用し、コスト削減につながる飼育方法を明らかにする。 | ○種苗生産期の油膜除去方法について、他魚種で実績のあるシャワー式の設置方法を検討した。 ○養殖期における波長(自然光・赤色・青色・緑色)・日長(24h・18h・12h・8h)のマハタの成長に対する影響を調べた。 |
|
| ブリ類に対する抗菌剤の効果的な使用法の開発 | 令和5~9 | 水研センター_魚類検査室 | EP飼料への抗菌剤の展着による効果的な投薬方法を確立するため、各種の展着剤を用いてモイストペレット(MP)との比較を行い、マニュアル化する。 | 2種類の展着剤を用いて、MP、市販の吸水性EP飼料及び非吸水性EP飼料に抗菌剤を展着させた餌を試験魚に投与し、血中濃度を測定した結果、EP飼料でも血中濃度は高くなり、展着剤の有効性が明らかとなった。 | |
| ノリ漁場生産力向上試験 | 令和6~8 | 栽培研_浅海調査室東予駐在 | 漁場生産力向上のためにクロノリを指標として効果的な栄養塩供給技術について検討する。産業技術研究所技術開発部において安価で持続性のある施肥剤を開発し、養殖資材である支柱を利用した簡便な栄養塩供給技術を開発する。 |
〇ノリ漁期中(10~3月)に毎週ノリ漁場環境調査を実施し、「ノリ養殖漁場栄養塩速報」として関係各所へ広報した。 〇化成肥料をゲル化剤で固めた施肥剤を試作し、栄養塩の溶出を分析した。 |
|
| サメを用いた高機能抗体作製技術開発 | 平成29~令和7 | 栽培研_増殖技術室 | ドチザメ科のサメを入手し、飼育管理し、愛媛大学から提供された抗原を用いてサメに免疫し、血液、組織等を愛媛大学に提供する。また、事業化に向けた飼育技術の高度化を図る。 | 〇エイラクブカ(ドチザメ科)の周年飼育をおこない、免疫試験に供した。 | |
| ブルーカーボンの評価手法及び効果的藻場形成技術の開発研究 | 令和3~6 | 栽培研_増殖技術室・浅海調査室・東予駐在 | 温室効果ガスの吸収源として期待されている藻場について、藻場タイプ別の二酸化炭素吸収量評価手法の開発や貯留量の全国評価を進めているところであり、本県では、CO2吸収源を増強する取組みとして、令和4年度からアオノリ養殖技術の改良とその増産効果を検証する。 |
〇人工採苗による増産効果を検証するため、人工採苗網と天然採苗網による養殖試験を実施した結果、人工採苗網の方が網1枚あたりの試験期間中の総摘採量(湿重量)が多かった。 〇アオノリ養殖業関係者を対象に、人工採苗技術の勉強会を開催した。 |
|
| 栄養塩類管理技術開発試験 | 令和5~7 | 栽培研_浅海調査室・東予駐在 | 瀬戸内海では貧栄養化による漁業生産の低迷が問題視されており、栄養塩濃度と漁業生産の因果関係についての科学的な検証が喫緊の課題となっている。栄養塩類が低次生態系に及ぼす影響の解明や一次生産を通じてより高次の水産資源に与える影響を調査し、適切な栄養塩類管理に資する。 | 〇燧灘海域における栄養塩類管理モデルの開発のために毎月1回海水の分析、観測データの整理を行い、とりまとめて愛媛大学に提供した。 | |
| アカウニ種苗生産の効率化と短期間での中間育成技術の開発 | 令和6~7 | 栽培研_増殖技術室 | 高価格で取引されるアカウニを効率的かつ安定的に生産するため、陸上養殖施設による種苗生産の効率化と短期間での中間育成技術の開発を行う。 |
○従前の手法に沿って種苗生産を実施し、改良対象の洗い出しをおこなった。 |
【水研センター】:農林水産研究所_水産研究センター
【栽培研】:農林水産研究所_水産研究センター_栽培資源研究所