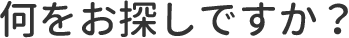本文
審査請求人の子に係る平成11年度学力検査成績等一覧表等案件
第1 審査会の結論
平成12年10月25日付けで愛媛県教育委員会教育長(以下「実施機関」という。)が行った非公開決定は、妥当である。
第2 審査請求に至る経緯
1 審査請求人は、平成12年10月13日、愛媛県情報公開条例(平成10年愛媛県条例第27号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、愛媛県教育委員会(以下「県教委」という。)に対し、
(1) 審査請求人の○○(以下「本人」という。)に係る平成11年3月に実施された高校入試の成績(学力検査及び内申点)が分かるもの
(2) 平成11年3月に実施された高校入試に係る○○高校の合格者の学力検査の最低点数が分かるもの
(3) 本人の不合格理由が分かるもの
(ただし、県教育委員会が保存している公文書に限る。)についての公開の請求を行った。
2 県教委から公開請求に対する決定に係る権限を委任されている実施機関は、平成12年10月25日付けで、前記1(1)及び(2)の文書については以下の公文書を特定した上で、それぞれ次の理由を付し、非公開決定(以下「本件処分」という。)を行った。
(1) 平成11年度学力検査成績等一覧表(以下「本件公文書1」という。)
条例第7条第2項第1号該当
個人に関する情報であって、特定の個人が識別できるため。
(2) 平成11年度合格者成績調査表(以下「本件公文書2」という。)
条例第7条第2項第7号該当
高等学校入学者選抜の望ましい在り方に反することになり、高等学校入学者選抜の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(3) 不合格理由書(以下「本件公文書3」という。)
該当する公文書は、作成していないので存在しない。
3 本件処分の通知を受けた審査請求人は、これを不服として、平成12年12月12日、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定に基づき、県教委に対し審査請求を行った。
4 なお、県教委は、審査請求書に行政不服審査法第15条に規定する法定記載事項について記載漏れ等があることから、平成12年12月22日付けで、審査請求人に対し補正命令を行い、平成13年1月31日に、審査請求人から補正書が提出されている。
第3 審査請求人の主張する審査請求の理由
審査請求人が、審査請求書及び実施機関の非公開理由説明書に対する反論書において主張する審査請求の理由は、おおむね次のとおりである。
1 本件公文書1について
本人の成績が分かるものを請求していたのに対し、公開決定においては、本件公文書1が特定されており、請求人の意図しているところより多分におおげさになっている。
2 条例第7条第2項第1号の非該当性について
(1)本人は、バスケットボールの有名選手であったので、平成10年に続き11年も不合格となったことが特異な出来事として、地域社会等において知られており、特定個人が識別される条項は該当しない。
(2)本人は、PTSD(心的外傷後ストレス障害)症状を発症し、この状態は不合格時点から始まり原因は明らかである。よって、条例第7条第2項第1号ただし書イに該当する。
(3)本件公文書1を作成したのは公務員であり、これは当然職務遂行の内容に係る部分に当たり、第7条第2項第1号ただし書ウに該当する。
3 条例第7条第2項第7号の非該当性について
○○高等学校の合格者最低点のみの公開を求めており、他の県立高等学校の合格者最低点の公開を求めているのではない。実施機関が、すべての県立高等学校の学力検査の合格者最低点が公開された場合、その数字が一人歩きして、各県立高等学校の学力レベルのランク付けにつながるおそれがあるとするのは、拡大解釈、牽強付会のそしりを免れない。
また、本条項のどこにも試験に係る事務に関しては、一切非公開であるとは明記されていない。
4 本件公文書3について
理由があるから不合格にしたのであって、本件公文書3が公文書として存在しないのであれば、現存している本人の点数と合格者最低点数が合否の妥当性及び正当性を判断する上において重要視される。
なお、当入試に関し請求人が幾度か質問した教員が現在も○○高校に在職しているので、この件に関しては詳細に知っているはずである。
第4 実施機関の非公開理由
実施機関が行った非公開決定の理由は、おおむね次のとおりである。
1 条例第7条第2項第1号の該当性について
本件公文書1には、受検者の氏名、受検番号、学力検査の成績等が一覧の形で記録されており、これらは、条例第7条第2項第1号本文に規定する個人に関する情報であることは明らかである。また、これらの情報は、同号ただし書のいずれにも該当しない。
2 条例第7条第2項第7号の該当性について
本件公文書2には、志願者数、最高得点、最低得点等の情報が記録されており、これらの情報が公開されると、高等学校入学者選抜の望ましいあり方に反することになり、高等学校入学者選抜の適正な遂行に支障を及ぼす次のようなおそれがある。
(1)学力検査の合格最低点が公表されると、1点の差を争う過度の受検競争をあおり、学力偏重の志望校選びの傾向を強めることとなる。
(2)すべての県立高等学校の学力検査の合格最低点が公開された場合、その数字が一人歩きして、各県立高等学校の学力レベルのランク付けにつながるおそれがあり、各高等学校が推進する特色ある学校づくりを阻害することとなる。
3 本件公文書3について
本件公文書3を非公開としたのは、作成されておらず、存在しないためである。
第5 審査会の結論の理由
1 本件公文書について
(1)本件公文書1について
本件公文書1は、平成11年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施細目(以下「実施細目」という。)において高等学校長から県教委への提出が義務付けられている公文書であり、これには、受検者の氏名、受検番号、出身校、性 別、学力検査の成績、学習記録評定合計、特別活動等の段階分けによる評価及び合否区分が一覧の形で記録されている。
この点について、審査請求人は、本人の成績の分かるものを請求していたのに対し、公開決定においては、本件公文書1が特定されており、請求人の意図しているところより多分におおげさになっていると主張するが、当審査会で調査したところ、県教委が保有する公文書として、本人の成績が分かるものは本件公文書1のみであり、公文書の特定に問題はないと認められる。
(2)本件公文書2について
本件公文書2も本件公文書1と同様、実施細目において県教委への提出が義務付けられている公文書であり、これには、志願者数、受検者数、合格者数、最高得点、最低得点、総得点、平均点、15点以下の者の人数及び合格者の総点度数分布の情報が記録されている。
(3)本件公文書3について
実施機関は、各受検者の不合格理由を記録した文書までは作成していないと主張しているため、平成14年1月30日に当審査会会長が実施機関に赴き、当該入学者選抜に係る関係書類の調査を実施したが、当該公文書については、存在していないことが認められた。
2 条例第7条第2項第1号(個人に関する情報)の該当性について
条例第7条第2項第1号は、本文で個人の尊厳及び基本的人権を尊重し、個人のプライバシーを最大限に保護するため、特定の個人が識別できる情報は、原則として非公開とする旨を規定し、ただし書において、「ア法令、条例若しくは実施機関の規則(規程を含む。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」、「イ人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」、「ウ当該個人が公務員(国家公務員及び地方公務員)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員の氏名に係る情報にあっては、公にすることにより、当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該情報を除く。)」については、本号本文に該当する情報であっても、公開しなければならないと定めている。以下、本件公文書1に記録された情報について、本号の該当性を判断する。
(1)条例第7条第2項第1号本文の該当性について
条例第7条第2項第1号本文は、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、非公開とすることを定めたものである。
本件公文書1には、前記1(1)のとおり、受検者の氏名、受検番号、出身校、性別、学力検査の成績、学習記録評定合計、特別活動等の段階分けによる評価及び合否区分が一覧の形で記録されており、これらの情報は、同号本文に規定する個人に関する情報に該当するのは明らかである。
(2)条例第7条第2項第1号ただし書アの非該当性について
条例第7条第2項第1号ただし書アは、法令、条例若しくは実施機関の規則(規程を含む。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているものは、個人情報であっても公開することを定めたものである。
この点について、審査請求人は、本人は、バスケットボールの有名選手であったので、2年続けて不合格となったことが、地域社会等において知られており、特定個人が識別される条項に該当しない旨主張する。仮に審査請求人の言うように不合格の事実が地域社会等に周知されていたとしても、それは単に不合格の事実のみが知られているのであって、本件公文書1に記録されているような本人の学力検査の成績や学習記録評定合計等の具体的な事実が知られているのではない。
また、これらの情報は、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているものではなく、条例第7条第2項第1号ただし書アに規定する情報に該当しないことは明らかである。
(3)条例第7条第2項第1号ただし書イの非該当性について
条例第7条第2項第1号ただし書イは、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報は、これを公開するということを定めたものである。
「公にすることが必要であると認められる情報」とは、非公開とすることによって保護されるプライバシーと公開することによって保護される人の生命、健康、生活又は財産といった公益の程度を勘案した上で、公益が優越する場合をいうが、本件公文書1は、前記1(1)のとおり、入学者選抜に係る個人の成績等が記録されており、これらの情報を公開しなければ、人の生命、健康、生活又は財産の保護に支障を及ぼすとは認められず、条例第7条第2項第1号ただし書イに規定する情報に該当しないことは明らかである。
なお、審査請求人は、本人のPTSD(心的外傷後ストレス障害)の発症が不合格時点から始まり原因は明らかである旨主張しているが、本件公文書1が公開されなかったことによる本人の病気の発症との因果関係と本件公文書1に記録された情報が条例第7条第2項第1号ただし書イに該当するかどうかの解釈とは無関係であるといわざるを得ない。
(4)条例第7条第2項第1号ただし書ウの非該当性について
条例第7条第2項第1号ただし書ウは、公務員の職務に関する情報は、行政事務に関する情報であるとともに、当該公務員の個人の活動に関するものでもあるが、行政執行の公正・透明性を高める見地から、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分については、仮に特定の公務員が識別されることになっても公開することを定めたものである。
この点に関し、審査請求人は、本件公文書1を作成したのは公務員であり、これは当然職務遂行の内容に係る部分に当たり、ただし書ウに該当する旨主張する。確かに、本件公文書1は、公務員が職務遂行上作成した公文書であると認められる。
しかしながら、これに記録されている情報は、前記1(1)のとおり、受検者の氏名、受検番号、出身校等公務員以外の者の個人情報であって、当該公文書を作成した公務員に係る情報ではないことは明らかである。したがって、公務員が本件公文書1を作成したことをもって本号ただし書ウの規定が適用されるという審査請求人の主張は採用できない。
3 条例第7条第2項第7号(事務又は事業に関する情報)の該当性について
条例第7条第2項第7号は、公にすることにより、県の機関又は国等の機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報は、非公開とすることを定めたものである。以下、本件公文書2に記録された情報について、本号の該当性を判断する。
(1)まず、本件公文書2は、高等学校入学者選抜という県が行う事務の遂行上作成された公文書であり、当該公文書に記録された情報は、本号アの「県の機関が行う試験に係る事務に関する情報」に該当することは明らかである。
(2)次に、本件公文書2に記録された情報を公にすることにより、「当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があるかどうかについて検討する。
審査請求人は、○○高等学校の合格者最低点のみの公開を求めており、他の県立高等学校の合格者最低点の公開を求めているのではない。実施機関が、すべての県立高等学校の学力検査の合格最低点が公開された場合、その数字が一人歩きして、各県立高等学校の学力レベルのランク付けにつながるおそれがあるとするのは、拡大解釈、牽強付会のそしりを免れないと主張する。
しかしながら、条例は県民一般に対する公文書公開制度を定めるものであり、請求者の別によって公開決定の内容に差異が生ずるものではない。仮に審査請求人の主張を認めるとするならば、他の者が他の県立高等学校の合格者最低点を公開請求すれば、同様に公開され、これらの情報が総合されると、すべての県立高等学校の序列化が可能となり、過度の受検競争をもたらすおそれがあることは否定できない。
(3)以上のとおりであるから、本件公文書2に記録された情報は、条例第7条第2項第7号に規定する当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報と認められる。
4 本件公文書3の作成の必要性について
本件公文書3は、前記1(3)のとおり不存在であるが、審査請求人は、当該公文書の存否にとどまらず、その作成の必要性について言及しているものと考えられるので、これについて、以下検討する。
(1)高等学校への入学については、学校教育法施行規則第59条第1項の規定により、調査書及び学力検査の結果等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長がこれを許可することとされており、本県の場合も、県教委において入学の合否の判断基準となる平成11年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項及び実施細目を定め、これらに基づく選抜を実施した上で、各高等学校長が入学の許否を決定することとなっている。
(2)実施細目によると、高等学校長は、報告書(調査書及び学習成績等一覧表)、学力検査の成績、面接及び実技テストの結果を資料とし、当該高等学校、学科等の特色を踏まえて、その教育を受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して選抜を行わなければならないとされている。また、合否の判定に当たっては、調査書中の出欠の記録、行動の記録、諸活動の記録及び総合所見並びに特別活動の記録、面接及び実技テストの結果等を十分重視し、総合的に判定することとされている。つまり、高等学校長が入学の許否を決するに当たっては、学力検査の結果及び調査書の成績評価等の諸資料に基づき、受検者が一定の要件を備えているか否かを教育的見地に立って、総合的に判定すべきものであり、その性質は、自由裁量行為であるとされている。しかし、自由裁量行為といいながらも、学校長自らが定立した条件に合致する場合(例えば、選抜試験において基準点以上を獲得した場合等)には、特段の事情がない限り、入学不許可処分にすることは許されないと解されている(和歌山地裁昭和48年3月30日判決参照)。
(3)ここで審査請求人は、理由があるから不合格にしたと主張する。確かに、不合格となったことについては何らかの理由があったものと推察はされる。しかしながら、一般的にいって、入学試験をはじめとする各種の選抜事務においては、合格者を選抜することにより結果的に不合格者が特定されるのであるから、既に特定された不合格者ごとに改めて不合格の理由を記録することは行われていない。したがって、高等学校入学者選抜においても、各受検者ごとに本件公文書3を作成しなければならないとする必要性があったとは認められない。
(4)なお、審査請求人は、当該入試に関し請求人が幾度か質問した教員が現在も○○高校に在職しているので、この件に関しては詳細に知っているはずであると主張するが、このことと本件公文書3が不存在であることは無関係であるといわざるを得ない。
5 その他
当審査会は、実施機関が行った非公開決定の是非を審査することを任務とするものであり、審査請求人の主張する公務員の地位利用による不正行為、公文書の不実記載等の事実関係を調査する立場にない。
6 まとめ
以上の理由に基づき、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断するものである。
なお、本件公文書3については、前記4で述べたとおり、作成の必要性を認めることができない。
別記
|
年月日 |
処理内容 |
|---|---|
|
平成13年3月7日 |
審査依頼(諮問)受理 |
|
平成13年4月9日 |
実施機関からの非公開理由説明書受理 |
|
平成13年4月18日 |
審査請求人に非公開理由説明書送付 |
|
平成13年6月28日 |
審査請求人からの反論書受理 |
|
平成13年7月3日 |
実施機関に反論書送付 |
|
平成13年7月18日(第1回審査会) |
審議 |
|
平成13年11月5日(第2回審査会) |
審議 |
|
平成14年1月10日(第3回審査会) |
審議 |
|
平成14年1月30日(第4回審査会) |
審議 |
参考
|
職名 |
氏名 |
現職 |
|---|---|---|
|
委員 |
門田 圭三 |
南海放送 株式会社 常任相談役 |
|
会長職務代理 |
藤山 薫 |
弁護士 |
|
委員 |
望月 清人 |
松山大学教授 |
|
会長 |
百地 章 |
日本大学教授 |