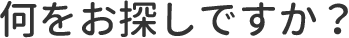本文
令和7年度10月知事定例記者会見(令和7年10月16日)の要旨について
日程:令和7年10月16日(木曜日)
時間:11時00分~11時03分
11時24分~12時01分
場所:知事会議室
(日本経済新聞社(幹事社))
それでは時間になりましたので始めさせていただきます。本日はまず、知事から、冒頭に発言があると聞いております。それではよろしくお願いします。
(知事)
はい。まず、いよいよ明後日10月18日から11月3日までの17日間、アートベンチャーエヒメフェス2025が開幕しますので、触れさせていただきたいと思います。とべもり+(プラス)を中心とした県内4エリア、八つのゾーンを舞台に、県と東京藝術大学が連携協定を結びましたけれども、それに基づいて初めて共同開催いたします芸術祭、アートベンチャーエヒメフェス2025(ニーマルニーゴー)が開幕いたします。
フェスでは、公募の結果、295組、334作品の応募の中から選ばれた23組と、内子・小田で、これが本当に初めての試みになりますが、地域と芸術舞台をつなぐ役割を果たしていただく人材育成、ひめラーの皆さんや住民の皆さんとともに作品を制作いただいた1組の合計24組の参加アーティストが、各会場のここにある豊かさを表現した作品を展開してまいります。
開幕初日の10月18日には、東京藝術大学の日比野学長をお迎えし、とべ動物園のアニマルステージにおいて、参加アーティストが一堂に会するオープニングセレモニーを開催いたします。
会期中は、シェフとアーティストがコラボした食のプログラムや、各会場・地域との連携イベントを順次開催するほか、お得な料金で楽しめる周遊バスツアーなど、盛りだくさんの内容となっています。また、この期間中、恒例となりましたえひめ愛顔(えがお)の子ども芸術祭2025(ニーマルニーゴー)や障がい者芸術文化祭、こちらとも連携したプログラムを展開いたします。
とべもり+(プラス)を中心に開催いたしますので、ぜひ、県民の皆さん、会場に足を運んで、異次元な空間を楽しんでいただきたいと思います。以上です。
(日本経済新聞社(幹事社))
それでは会見に移ります。記者クラブからの代表質問は1問です。首相指名選挙の所感について伺います。15日に予定されていた首相指名が、10月下旬にずれ込みました。
このことにより、政治空白が生まれ、物価高などの財源となる補正予算の成立が遅れることとなり、地域経済にも影響が出ると思われます。首相指名がずれ込んでいる現状を知事はどのように受け止めていますか。
(知事)
そうですね。これはもう当初からずっと申し上げてきたことなんですけれども、これは県だけにとどまらず各業界もそうですし、基礎自治体もそうですし、本当に今いろいろな課題が山積をしています。
その中で国が決断をしなければ、身動きが取れない分野が非常に多くなってきていますので、もうともかくその現状、現場の現状を受けて、与党も野党も与野党問わずですね、
国会議員は何のために仕事をしているのかという観点に立って、一刻も早く課題解決に向けた議論を進めていただきたいというふうな思いを言い続けてまいりました。
ただ、首相選挙これは日本のトップリーダーを決めることですから、いろいろな話し合いがあって仕方がない面もあるのかもしれないけれども、それにしても長引いてるという感想を持っています。
そして、その長引く中でニュースでしか分かりませんけれども、何て言うんですかね。
国家戦略をベースにした大胆な政策議論であるとか、あるいは現状課題に対する危機感、そこからにじみ出るスピード感こういったものがあまり見えてこないんですね。単なる数合わせではなくて、もちろん今安定多数を持っている勢力もいませんから、致し方ない点はあるのかもしれないけれども、今そこにある問題とそれから将来この国がどうなっていくのかという重大な責任と使命を負っているという、やっぱりそういった気持ちが国民に伝わるようなスケジュール感と議論を早くやっていただきたいと切にこれを願っています。
昔の総裁選挙というのは、もっと大胆だったと思うんですね。すごい国民がわくわくするようなビジョンであるとか、政策がそれぞれの候補者から出てきて、本当にあのスケールの大きな議論が、もちろん多数派工作とのは昔からあったが、あったことは間違いないんですけれども、その前提としてそのわくわく感、この人がなったらこんなふうになるのかなとひょっとしたら日本の経済こんなふうに成長していくんのではないかなという、そんな議論を通じた期待感というのが伝わってきた時代が僕の若いときにはあったんですけれど、今回それがないというのが本当寂しいですね。
特に国際情勢がこういう状態なっていますから、そこと立ち向かっていく国家間戦略というものは必須条件になってきていると思うので、もう本当にもう終盤になってきていますけれども、せめてそれを感じさせるような議論が、この限られた時間の中で見えてくることを期待したいと思います。
(日本経済新聞社(幹事社))
ただ今の答弁について、質問のある社はお願いします。
(愛媛新聞社)
すみません。愛媛新聞です。お願いします。関連してなんですけれども、今、自民党と日本維新の会でですね、連携の協議をし始めていると思うんですけれども、今後のですね、影響であるだとかを知事はどう見ていらっしゃいますでしょうか。
(知事)
いや、分からないですね。あくまでも知事という立場、これは知事会もそうなんですけれど、全国知事会でも最後に申し上げた意見を言わしていただいたのですが、おそらく前回の参議院選挙の結果を踏まえると、今後10年は政局は不安定にならざるを得ないと思います。参議院選挙は3年ごとの選挙ですから、半分改選の状態が続いていく。その中で前回は圧倒的に野党が勝った。その前は圧倒的に与党が勝っているという状況になっていますから、その中での今の議席数と、次に6年前に絶対的に与党が勝った体制が、自公政権も変わりましたから、これどうなってしまうのかなということを考えると、その影響で10年間ぐらいは同じような状況が続く可能性が出てきていると、最低でも今の前回の状況から踏まえると6年間は不安定になることが確定してしまっていますから、その次の選挙結果次第ではこれがまたさらに延長していくという状況になってくるので、本当にしっかりとした政権の運営についての議論は必要だとは思います。ただ、その前提として先ほど申し上げたような混沌とする国際情勢や経済情勢を鑑みると、大胆な国家戦略ビジョン等々が必要になってきますので、あくまでもそれを国民に見える形で明確に議論するということが大前提になると思いますので、その点を早くやっていただきたいのですが、ただ、昨今のサラリーマン化してしまっている政治家の情勢を考えますと、おそらくこことここが組み合ったら、例えば国と地方でもまた意見が違いますから地方の現場では反対が起こるとか。おそらく、自身の生き残りを優先するようなアクションがですね、最終場面でもどんどん出てくる可能性は十分あると考えますので、これ維新は特に大阪では自民党と徹底的に対決してきた歴史がありますから、ここらあたりを国、国会議員レベルでの話し合いと戦って戦って戦い続けている地方現場の意見と、どうすり合わせていくのかなというのは全く見えてないと思うので、方向性が決まったからといってそれで決定というわけにもいかなそうだなというふうに思っています。
(愛媛新聞社)
すいません。続けてなんですけれども、知事がおっしゃるように、まだ方向性が決まってから決定というよりか、連携するかどうかっていうところははっきりしないと思うんですけど、維新であれば例えば社会保障改革とかですね。定数の削減とかを訴えてきたと思うんですけど、このあたり、知事と同じような考えなのかなと私は思ってたんですけれども、いかがでしょうか。
(知事)
そうですね。僕もやっぱり今のイギリスというのはよく例に出したと思うんですけれども、イギリスも政治と国会が停滞して弱体化するのは国家としてどうなのかという意見から、定数の問題であるとか世襲制限に踏み切った経緯があります。
やっぱり質の高い、よりスキルアップした国会議員が必要だという世論が動かしたと思いますけれども、それによって今の体制が決まっていきました。これだけ政治と金の問題が浮上して、各政党が国民の不信感を払拭するためにやろうという状況になっていますから、事ここについては、例えば定数削減であれば、もうこれ野田政権時代に野田総理と当時の野党の党首であった安倍、当時の総裁が国民の前で約束したことであることを誰も覚えてないのかなと。それすら実現していない現状を鑑みると速やかにやるとか、それから野田党首が発言していた世襲制限もイギリスのように制度、やっぱりどう考えてもいろいろな政治資金規正法なんかでも、抜け道がありますから、そういったことにもメスを入れるという大胆な提案をするチャンスだと思うんですね。だからそこを今の議論の中で自民党がちょっとその辺がもう一歩踏み込まないというところが、公明党さんとの距離感が出たとか、ああいうふうなことにつながっているので、ここは一気に進めるチャンス、絶好のチャンスではないかなと思うので大胆にやっていくことで、何らかのプラスが生まれる可能性はあるのではないかなというふうには思います。
(日本経済新聞社(幹事社))
各社さん、他によろしいでしょうか。
それでは代表質問以外で質問のある社はお願いします。
(愛媛新聞社)
すみません。愛媛新聞です。四国中央市にある四国中央病院、旧県立三島病院についてお伺いしたいんですけれども、移譲時に交わした基本協定の中にあった新中核病院の再建築が白紙。経営状況の悪化から計画の白紙化に至っているという状況なんですけど、病院側は現状が続けば撤退もあり得るということで、さらなる支援を求めてますけれども、立地自治体の四国中央市の方は、当事者は、県と病院だというふうにコメントをしていると思います。知事は四国中央市側の声をどのように受けとめているのか教えていただけますでしょうか。
(知事)
そうですね。市長さんが変わったから基本方針が変わるというのは、外交が変わるようなものだと思うんだけれども。前の市長さんは、やはり市民の命を守るということに、県も市も共済もないと、だからみんなで協力してやろうというのを明確な方針を打ち出していましたので、それが市長が変わると、その方針すら変えるというのはちょっと理解ができないところがあります。
元々この問題というのは、三島に県立病院があったときに、非常にこれは厳しい状況で、新居浜病院もきっちりしないといけないということもあって、総合的に市も交えて方向性が決まったと聞いています。これちょっと私の前の時代なので、細かいところまでのやり取りまでは分からないんですけれども。その中で、三島とやがては川之江、合併したことによって、より良い病院を中核病院を作ろうということでは三者でも意見交換する中で決まっていった経緯がありました。
今問題になっているのは、三島の地区に中核病院を作るというプランでしたから。実は今、おそらく全国の病院は赤字経営になってるとこが多くなってきています。特に公立病院は、余計に採算の合わない二次救急であるとか、周産期医療であるとか、こういったものも使命感でやらないといけませんから、赤字要因は大きくなるんですけれど、そこに看護師不足という全国共通の問題も浮上して、病床が開けられない。これも赤字要因になっていると、だから民間も含めて非常に厳しい状況にあります。
この根本原因は、行政で言えば行政改革ですね、経営改革を行っても、それは経営改革というのは、支出を減らすということしかできなくて、収入を増やすためには、患者を増やすか、あるいは診療報酬を上げるか。これしかないんですよね。患者を増やすというのは現場でも一生懸命取り組んでいます。先ほどの看護師さんを確保するというのはそこの部分にもつながっています。問題は、この診療報酬制度で、これはもう国で決まってしまいますから。しかも、2年に一遍の改定がルールになっているので、今ご案内のとおり、先月よりも物価が上がった。さらに上がったっていう、こういうときにですね、2年に一遍の改定で追いつくわけがないんですよね。
だから、これが見えない限り、病院の経営の見通しが全く立たないと。先ほどこれ国会が停滞するというのはここも大きな課題で、これ国民の命全体に関わる問題なので、だから早くしてほしいということを申し上げてるんだけれども、そこが全く見えないので、厳しい状況にあると。その中で今問題になっているのは、県立病院ではなく元々の共済の病院であった川之江のまさに川之江地区の病院が赤字体質になって、共済としては、この現状の川之江病院の赤字をどうにかして埋め合わせなければ、次のステップに行けないというふうな声を上げ続けていますから。それを受けて昨年まで四国中央市は同じように、県もやります。でも、四国中央市も我が事、四国中央市民の命を守るということで、当然我が事として、バックアップするというのを明確にして、三者ができることを一生懸命やって乗り越えていこうという体制が組まれていましたから、ここがもし、そういう四国中央市民の命は県と共済が勝手にやればいいなんてなったら、ものが進むわけがないので、決してそんなことはまさか考えてはいらっしゃらないないのではないかなというふうに思っています。
(愛媛新聞社)
ありがとうございます。ちなみにすみません、追加なんですけれども、四国中央市側は県と希望が持てる話し合いをしたいというふうに言ってる部分もあるんですけど、今のところ何か具体的なアクションがあったりは。
(知事)
いや全く聞いてないです。何か聞いてます。
(菅副知事)
いや、特にないです。
(愛媛新聞社)
県の方から何かっていうことも。
(知事)
県はしょっちゅう言っていますね。まずこの川之江の問題があるので伊予三島の中核のときは県が前面に出てきますけれども、川之江、今起こっている問題については、そこをクリアしないとその次のステップいけないので、ぜひしっかりと一緒になってやってほしいというふうなメッセージを送り続けていると聞いています。
(愛媛新聞社)
承知しました。ありがとうございます。
(愛媛新聞社)
すみません。先ほどの病院の関連なんですけど、県の医療提供体制として、例えば三島の病院とか川之江の病院とかは、三島の病院が建替えたりができなかった場合に、需要として、そのエリアのですね、医療提供体制として満たせるのでしょうか。このあたりは分かりますでしょうか。
(知事)
まだそこの段階ではないと思います。
(愛媛新聞社)
なくても、白紙化されても問題はないというようなものなのでしょうか。
(知事)
いや、それはないと思います。問題はあると思います。もちろん。だからこそどうすれば、計画に近い形に持っていけるかというのをそれぞれがチーム、スクラム組んでやるということが大事だと思います。相手がどうだとかそういう話ではなくてみんなで考えていくことが大事なのではないでしょうか。
(あいテレビ)
すみません。あいテレビです。県の魅力度ランキングについてお伺いしたいです。愛媛県は今年32位となっておりまして、去年から四つ順位を下げました。それについて、知事の受け止めとこの魅力度ランキングアップについての施策みたいなものがあるのでしょうか。お願いします。
(知事)
これは誰が、どのような形で決めているのかさっぱ分からないです。高ければうれしいし、低ければなんか悔しいなというふうな思いは当然あるんですけれども。でも、誰がどういう基準で決めているのか、客観的な判断ができないので、あまりこれに引きずり回されるつもりは、僕の中にはありません。
だから例えば、去年よりは下がっているけど一昨年(おととし)よりはいいとかですね、一昨年(おととし)が34位だったと思いますから、それよりは上がってるというふうな見方もできますし、特に新幹線のない四国は当然のことながらハンディがあります。
四国のエリアというのが、軒並み、その影響で下位になってしまうというのは、こういうアンケートではどうしても出てきちゃうんですね。
他はもう全部、飛行機プラス新幹線で移動できる場所ばっかりなのに、四国だけはそれができないと、このハンディというのはもう致し方ないかなと。今の段階ではね。というふうには思っています。だから、そこは冷静に見極める必要があると思います。ただ、これだったら、もう客観的に見て刺激をいただくぐらいの指標として見つめています。もうちょっと次は上がるように、また頑張らなきゃねというようなことだけれども、今言ったような、四国という地理的なハンディを負っている以上は、例えば1位を目指すなんていうのはどだい無理な話であって、それぐらいの、なんていうかな、刺激をいただく指標として捉えてます。
(あいテレビ)
ありがとうございます。
先ほどの話の中で新幹線についての話が出たんですけれども、四国新幹線について、知事は今後どう進めていきたいかというお考えはありますか。
(知事)
そうですね、これもですね、今、地方創生の議論を知事会でやっていますけれども、まさにこの総裁選挙で、そういった大胆な政策展開の夢、ビジョンがないから停滞感が広がっていると思うんですね。例えばもっと早く。今、実は道路予算と比べると鉄道予算というのは本当に微々たるものなんですよ。B/C(ビーバイシー)もしっかり計算しながら、例えば、北陸の新幹線の延長線上というのは50万人ぐらいの人口規模なんですが、四国の新幹線が松山まで来た場合の周辺人口というのは60万人なんですね。岡山がもし拠点になったら、岡山はもう場合によっては中四国の拠点になる可能性もあるとか、いろいろな要因が出てきますから、そういった中で国がそれを受けてですね、将来の国づくりのために、もう一気に四国新幹線も北海道新幹線も敷設するんだと。それによって経済効果は絶対出てきますから、九州見ても明らかなように。あるいはもう一気に豊予海峡のトンネルまで夢を追うんだというぐらいのですね、国家としての大胆な戦略が総裁選挙で見えたらいいのではないかなというふうに思うので、実は今度の地方創生の本部長としての秋の提案をまとめるときに、今申し上げたことを国は語るべきだという要請を入れようというふうなことで議論を進めています。まさに愛媛県が新幹線を欲しいといったって、愛媛県が事業をやるわけではないので、まさに国が決めることだと思いますので、そこに期待したいと思っています。
(あいテレビ)
ありがとうございました。続いて別件なんですけれども、現在西予市が財政危機に陥っていることに関して、市町との連携の一環でこの支援を検討する予定などはありますでしょうか。
(知事)
はい、あのまあちょっとこれ、基礎自治体の財政状況、数値、推移とか、どういう形で進めてきたかということは正直言って当事者ではないので分からないです。で、一応あの県下の市町が健全になってほしいということで、ヒアリング等は行っております。その結果を受けてですね、まあ健全な財政運営ということについて、国も指導・助言、県も助言してきたところでございます。西予市はですね、財政悪化の要因というものを正式に発表していますけれども、交付税が段階的に減少したにもかかわらず、合併以降の地域間バランスに配慮したまちづくりを続けたこと、まあこれはあの必要だと思うんですね。僕も市長として合併しましたけれども、まあ例えば松山市と北条市と中島、その中で当然合併された側の中島や北条にどれだけの細かい配慮をすればいいかということは実際やっていましたから、これは十分配慮したまちづくりというのは必要だと思います。ただそこはあの西予市の場合、ゼロメーターから1400メーターというですね、県下でも有数の高低差がある、合併によってそういう市になりました。明浜の海から四国カルストまで網羅していますし、海もあり山もあり、しかも陸地部においては宇和盆地と野村町というのはかけ離れていますから、山で、こうしたところにすべて配慮していくということで、大変ご苦労があったんだろうというふうに思います。そこにもってきて、西日本豪雨災害が襲いました、襲われました、特にこの時については、野村町が多大な被害を受けたということ、それから宇和町も大きな被害を受けたということでその対応に追われたという特殊要因もあります。そういったとこでコロナもあって、行財政改革への取り組みが停滞したことが要因として西予市の発表で挙げられていました。これあのそれぞれは要因としては十分特殊要因ですから、理解できるものではないかと思います。
西予市は県内の市町の中では主な財政指標はいずれもあまりよくない状況であるのですが、健全化判断比率、ここはですね、早期健全化基準を下回っています。これあのぜひ後で調査していただけたらと思うんですけれど、ここは下回っていますので、直ちに財政運営上、支障が生じるということはないだろうと、直ちにということ。ただ、令和6年度決算、速報値ですけれども、これを見てみますと経常収支比率がやっぱり100%を超えていると、大体これ90からまあ高いところで95ぐらいかな、僕が松山市のときは89ぐらいだったと思います。100を超えているということになると、これ固定費が多いということですから、財政が硬直化するんですね、そういう傾向はこの数字で出てきているということ。それからもう一つは財政調整基金ですね、この残高が今年度予算編成時点で3億円、9月の補正で13億となっているというふうなことも確認いたしました。で、特に実質公債費比率、これがちょっと上昇傾向にあるので、先ほど直ちにということはないので、この段階で逆に危機感を表に出して、自らも汗をかき、そして市民の皆さんと共有して痛みを分かち合うことも必要になってくると思うのですが、この時点でやるということで、健全化に向けての道筋というのは立っていくと信じています。この時点でやることがすごく大事だと思いますので、市の改革に向けた姿勢を評価はしたいというふうに思っています。
(あいテレビ)
分かりました。ありがとうございます。ちなみに、この先ほど直ちに支障があるわけではないが今やるべきだっていう説明いただいたんですけれども、県として何か支援をしたり、何かそういうのはあるんでしょうか。
(知事)
もちろんやります、お金というよりはいろいろなテクニックの問題があります、例えば有利な起債を活用するとかですね、この事業は実は交付税算入が高い起債の方法があるよとか、いろいろなテクニカルな問題もあると思いますので、余地が、そういった点については県の方でしっかり精査して、アドバイス、助言を行っていきたいなというふうに思っています。
(あいテレビ)
分かりました。ありがとうございます。
(テレビ愛媛)
すいません。テレビ愛媛です。県内でのアリーナの整備についてお伺いします。
松山市は松山駅の西側でアリーナの整備を計画されている中で、先日松前町も都市型のスポーツ施設の整備とともに将来的なアリーナの整備について、町長が構想を発表されました。松山駅周辺は再開発の遅れが指摘されていますけれども、このアリーナを巡って県内で議論が相次ぐといいますか、活発化されている状況について、知事どのように受け止めてらっしゃるでしょうか、お聞かせいただけますでしょうか。
(知事)
そうですね。これは市が、あるいは町がビジョンを掲げて行っていく中での一つの事業だと思います。だから、大事なことはやっぱりトータルプランの中で単体でアリーナがあるのではなくて、まちづくりのビジョンの中でアリーナがどう位置づけられているかという、そこのところが非常に重要なのではないかなというふうに思いますので、そういった中でこちらもぜひやりたい、こちらもぜひやりたいということで、なんていうんですかね、いい意味での競争というかな、競争とまでは言わないんだろうけれど、提案が複数出ることはむしろ好ましいことではないかなというふうには思います。ただJR松山駅というのはちょっと特殊要因があって、もう、そもそもの発端は、平成11年のキックオフになるんですけれども、事業展開、高架事業は県が担って、周辺のまちづくりは市が担うっていうことの約束事のもとに立ち上がって、高架事業はご案内の通り既にもう完成して、県がやるべき約束した事業というのは、あとは駅舎の撤去と抜いた道路の(鉄道の延伸の用地を確保した)、その整備なんですけれど、これももう秒読み段階で、県が約束した事業は全て完了の時期を迎えます。この10年の間にプランができて、同時着工、ないしは完了したと同時に着工というのが理想的だと思っていたので、ここずっと松山市さん早くやった方がいいのではないですかというのは言い続けてきたんですけれど、これがちょっと今でも見えないというのは残念に思っています。アリーナというのは今年になって出てきた話なので、ちょっと懸念しているのは、今から計画してやったら一体いつできるのか。常識的に考えても、7年も8年も10年も先のことになるのかなというふうに思います。それと、狭い土地の中でどれだけのものができるのか。これ民間投資を呼び込むという発想でやるならば、やっぱり事業者にとってバスケットというのは必須ではあるものの、それだけでは運営ができない。たかだか30試合だけですから。それ以外のマネジメントも含めてどうするのかという議論を早くやらないと、どんどん遅れていってしまうというところが懸念かなと。そもそもアリーナは、もう一つ議論しておいてほしいなと思うのは、バイクスの社長(会長)のコメントを聞いてると、当面コミセンでやって、コミセンがもう2500しか入らないので、今県に相談が来ています。砥部の、次の段階で砥部の体育館が果たして使えるのか否か、結論は出ていません。4、5千人の観客が呼べないと、なかなか次のステップに行けないので。でもこれをやるだけでも5年ぐらいかかると思うんですよ。できてから何年か使いますから。そこも空白になってしまう。その後に成功、そのステップで成功した場合に初めてアリーナという、こういう2段戦略になっていますから、バイクスがアリーナに本格的に着手するのは、そういういった意味では5年先以降のことになるのではないかなと。そうするとその間に西側はどうするのかなという、この議論が全くないのでちょっとそこは心配しています。
(テレビ愛媛)
先行きについてのこう不透明さがかなりあるというようなところのご認識ということでしょうか。
(知事)
そうですね。だからトータルビジョンが必要だということを申し上げてきたんですけれども、あとは事業費が全く見えないということになると、民間事業者は全く計画が立てられないので、早くこれぐらいではないかというぐらいは出した方がいいのではないかなと思いますね。
(テレビ愛媛)
ありがとうございます。
(愛媛新聞社)
すいません。愛媛新聞です。
関連してなんですけれども、現在松山市は基本計画をアリーナ関連して作って進めていて、松前町はまだ構想が出たという段階だと思うんですけれども、知事も複数提案が出るっていう、これも好ましい、いろんな競争が起きるのは好ましいというお話ありましたが、最終的にはそのどちらかに調整をしていくものなのかと思っておりますが、県としてこれの、その場所であるだとかに、その調整に関わっていくとか。動きはないですか。
(知事)
ないです。
(愛媛新聞社)
もうこれはあくまでも自治体同士で。
(知事)
そうですね。もちろん協力はしていきますけれど、決めるのはもう基礎自治体のまちづくりの競争になりますから、それは県が関与することではないというふうに思います。むしろ、事業者との話し合いの中で決まっていくのかなと。公設である場合だったら別ですけれど。おそらくどっちも民間活力を活用するというふうなことのようなので、そうなると事業者との話し合いが決定要因になるのかなというふうに思います。事業者もただ単にさっき申し上げたように、アリーナそのものというのはバスケットだけでは成り立たないので、365日の中でどう、どれだけ活用するか。例えば展示会であったり、コンサートであったり、そのためにどこが建設し、どこが運営費を出し、どこがマネジメントをしていくかというところも明確にしないと、なかなか事業者との話というのは進まないのかなというふうには、感想としては思いますね。
(日本経済新聞社(幹事社))
その他ございませんでしょうか。
(NHK)
すいません。NHKです。お願いします。関連してなんですけれども、やはり松前町さんがまた新たに加わったとなると、関係する機関がまた一つ増えたということで、意見集約というか、より話の進め方が難しくなってくるところなのかなと思います。以前知事がリーダーシップが、トップのリーダーシップが大事だということもおっしゃってましたけれども、その辺り、意見をどういうふうに集約されていくべきかというか、所感というか。
(知事)
いや、分からないですね。その地域のまちづくりのビジョンが示されたときに、次にはそれが町民の皆さんとの話し合いの中で積み上げられていく。いわばトップの役割は本当に僕は二つだけだと思ってるんですけれども、真っ白なキャンパスに鉛筆で下絵を書くこと。まさにここがビジョンだと思いますね。次のもう一つの役割は、そのビジョンを皆さんに提示して参加者を増やしていくということ。要は理解を深めていくということですよね。その理解が深まると、じゃあみんなで一緒になって色をつけましょうという段階に入っていきますから、そこがスムーズにいった場合に、みんなが筆をとって絵具を使ってみんなで絵を、色をつけながら完成品になっていくという。だから、トップの役割というのは下地の絵を書くことと、みんなが参加する、楽しく参加する、前向きに参加する環境を整えるということがリーダーの役割だと思うので、そこはそれぞれの地域のリーダーがどう考えてるか分かんないですけれど、あくまでも僕の個人的な思いですから。僕はそういう視点で今後どう展開するかというのを興味深く見ています。
(日本経済新聞社(幹事社))
その他ございますでしょうか。
(愛媛新聞社)
すみません。ちょっと全く話変わるんですけれども、秋祭りのシーズンになっていまして、近年、祭りに関連して人同士の喧嘩(けんか)が発生したりしてですね、祭りのルール自体を各団体さんが見直したりしていると思うんですけれども、そもそも祭り自体は県の観光振興の策としても、いわゆる呼びものとしてですね、使ってるようなところもあるとは、そういう位置づけもあると思うんですが、現状、危険な行為等々がですね、発生しているような状況を知事としてどのように見ていらっしゃいますか。
(知事)
非常に残念極まりないですね。
しかもそれが、大半の方々は平和運行を前提に祭りを盛り上げていこう、純粋に楽しもう、多くの人に喜んでもらおうという思いで、もうこれ大半の人がやっているんですよ。
本当に一部の人たちの暴走というものが祭り全体のイメージを失墜させるということにつながりますから、それをトラブルを起こした方々に対しては憤りしか感じません。
で、ただそれをこう、なんて言うんですかね、実現してしまったことについての運営上の責任というのは当然ありますから運営者に、やっぱりそれを事態を深刻に受け止めて、多くの大半の方々がしっかりやっているということを重みとして、きちっとした対応をしていくと、再発防止に速やかに取り組むということ、で、起こしてしまった方に対しては厳しく対応するということ、これを徹底するしかないのではないかなと思います。
今年になって新居浜市長が記者会見をして、しっかりと事前な対応をして呼び掛けを続けていますので、僕も西条で起こった話というのは、そんな西条はこれまであまり聞いたことがなかったんですけれど、やっぱりここ祭りの実行委員会、で、場合によっては市長さんも同じように呼び掛けられたらいいんじゃないかなというふうに思います。
(愛媛新聞社)
すみません。これ、県の範疇(はんちゅう)ではないとは思うんですけれども、例えばそういった行為をですね、規制するような呼び掛けであるだとか、県としてできることは何かあるんでしょうか。
(知事)
県はですね、これは僕の権限ではないんですけれど、こんな問題が起こってるのでやっぱり気をつけていただきたいというのは、例えば県警本部長や、あるいは公安委員長にも連絡は話はしました。
(日本経済新聞社(幹事社))
各社さん、他によろしいでしょうか。
それではこれで会見を終わります。
(知事)
はい、どうもありがとうございました。
※議事録については、読みやすさや分かりやすさを考慮し、発言の趣旨等を損なわない程度に整理しております。