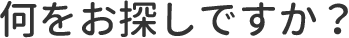本文
令和7年度4月知事定例記者会見(令和7年4月10日)の要旨について
日程:令和7年4月10日(木曜日)
時間:11時30分~11時50分
11時53分~12時03分
場所:知事会議室
(読売新聞社(幹事社))
それでは会見に移ります。記者クラブから代表質問は1問です。外国人材の受け入れについてお伺いします。
県内産業の担い手対策として、県では外国人材の受け入れに本格的に力を入れているところかと思います。一方で先日、県内の代表的な産業、造船業の企業が、国から実習生の5年間受け入れ停止処分などを受けたことが明らかになっています。県内産業にとっての外国人材の必要性や受け入れにあたっての現状の課題、また、それに対して、県としての今後取り組む受け入れ強化策をお伺いできればと思います。
(知事)
はい、先月、大手造船会社に対する技能実習計画の認定の取り消し処分が国から発表され、担当部局が同社へ問い合わせをさせていただきました。現在のところ造船受注に影響はないという回答がございました。
県は今回の処分に関しては、指導権限は有しているわけではなく、また、県が開拓して人材ルートを作っていますけど、大きな会社なので、直接(人材を確保している)なのでそのあたりの動向というのは、詳しいことは分からない状況でございます。ただ、関連企業や海事産業全体の人材確保への今後の影響はしっかりと見極めていく必要があると思っていますし、外国人材から見た県全体のイメージが低下しないよう、業界団体とも連携して、各企業に法令順守をさらに働きかけていきたいと思います。
本県産業を支える人材の確保については、急速な少子化の進行や若年層を中心とした転出超過などにより、年々厳しさを増しています。特に地方では技能実習生などの外国人材が地域産業の担い手として大きな役割を果たしているところでございまして、実際、愛媛県内の外国人労働者数も年々増加しております。国が集計した昨年10月末時点で、1万4550人、約1万5千人と過去最高の人数となっております。その半数が技能実習生でございまして、貴重な戦力として県内で活躍をしていただいています。
一方で送り出しの国であるアジア諸国の経済成長で、成長に伴って国の雇用環境を改善しておりますし、若干、今円高に振れてはいますけども150円近辺で張り付いていた円安によりまして、相対的な日本における賃金の水準低下がございます。昔のように無条件で日本が選ばれるというような状況ではなくなりつつありまして、国外はもとより国内でも人材獲得の競争が激化してきていると思います。
こうした状況を踏まえまして、県では今年度から、外国人雇用に係る企業向け相談窓口の設置、また住居等の受け入れ環境整備や、地域イベント等の交流事業に取り組む企業団体への補助制度の創設、そして帯同家族も含めた日本語教育や災害への備えに係る支援など人材定着や、多文化共生推進に向けた施策の充実強化を図っているところでございます。
また、人手不足が深刻な介護、そして先般も発表させていただきましたが航空分野での人材確保支援、県内教育機関等と連携した留学生の県内就職促進などにも取り組むこととしておりまして、企業ニーズや本県産業における課題を踏まえ、働き暮らす場所として外国人材から選ばれる愛媛を目指した取り組みを進めてまいりたいと思います。以上です。
(読売新聞社(幹事社))
ただいまの答弁に関しまして、質問のある社をお願いします。
(南海放送)
すいません。南海放送です。先ほど知事、関連企業や海事産業への影響は見極めていくということをおっしゃっていたんですけれども、もし今後必要に応じて県として考えられている対応策でありますとか、支援策というのがもしありましたら教えていただけたらと思います。
(知事)
そうですね。これはあくまでも、やっぱりまずは受け入れる企業さんがその人材を戦力にはなっていただくわけですけど同時に、やっぱりWin-Winの形にするためにはしっかりとした受け入れ体制を整えるということが重要ですから、そこは経営者への啓発、経済界と連携した啓発が必要だと思います。
同時に先ほど申し上げましたように、やっぱり定着していただくには、愛媛って、仕事もさることながら、休日も楽しいねというような環境がないと、なかなか定着にはつながらないと思うので、そういった面での文化交流であるとか、例えばこの前は結構人気があったのが、アジアの人は雪を見たことがないので、県内のスキー場のモニターツアーを実施する、そういったことで今、実は今年スキー場も四国の技能実習生、かなり来ているんですね。そういったようなところの後押しとかですね、きめ細かくやっていきたいなというふうに思っています。
(読売新聞社(幹事社))
各社さん他によろしいでしょうか。
それでは代表質問以外で質問のある社はお願いします。
(毎日新聞社)
先日、最新の南海トラフの被害想定が公表されましたが、愛媛県にもたくさん課題があると思うのですけれども、知事としては現時点で課題をどうお考えでしょうか。
(知事)
災害に関する情報は一喜一憂せずに、冷静に受け止めて正しく恐れて準備していくことが最も重要だと思います。被害想定の数字の大小、増減に振り回されるのではなくて、まずは冷静に増加した要因というものが、これ国のほうで計算しますので、それを分析するということが大事だというふうに思います。
これ国によりますと、細かいことがこの段階でも良く分かっていません。南海トラフ巨大地震による想定死者数が2倍に増加しているということでした。その要因は表で伝わってきている段階では、津波の浸水面積を2倍にしたということが背景にあるそうです。それまでは約3600ヘクタールの想定だったそうなんですが、これを8300にしたというふうなことであります。その結果対象が広がったために(津波による)死者数は約4倍というふうにしているのですけども、これ以上のデータ、分析データというのはまだ分かりませんので、その背景をしっかり分析する必要があると思います。
いずれにしても、今回の発表は発生した場合にですね、国難級の災害になり得るという強い危機感を持つというふうなことが大事であるということ、それから、最悪の場合の全体像を改めて地域社会全体で共有することが大事であるということ、そして、あらゆる主体が一丸となって対策を講じればその被害を軽減できるということも示しておりますので、ここがすごく大事な点ではなかろうかというふうに思います。いずれにしても、自助・共助の力の発揮が必要不可欠というふうに思います。
現在、県独自の被害想定の見直しを進めておりまして、今回公表された国の被害想定における新たな知見や対策等も、先ほど申し上げましたように分析して、そしてその上で取り入れながら作業を進めているところでございます。すなわち今回の結果を反映させることで、被害の抑制・軽減に有効なハード・ソフト両面からの対策の一層の充実を図るということでございます。
県民の生命・財産を守ること、いつも火災のときや城山のときにも申し上げましたように、行政としては最大の使命でございます。本県としても、人的・物的被害の抑制に向けまして、これまで緊急輸送道路・堤防等の整備、木造住宅の耐震化、家具固定の支援、津波避難対策の強化、登録者数全国1位を達成した防災士の活躍促進など、引き続き、全庁を挙げて防災・減災対策に取り組んでいきたいと思います。以上です。
(毎日新聞社)
今回の被害想定を反映した、県としての被害想定というのは、いつ頃を目途に公表されるんでしょうか。
(知事)
今年度中ということで準備を進めてるんですけども、先ほどのように新たな要因が入ってきましたので、まずは分析を急ぎたいというふうに思っています。
(愛媛新聞社)
愛媛新聞です。関連してお伺いします。今回の国の想定では津波の浸水面積が広がったことで死者数が多くなるという結果だったと思いますけれども、条件として、早期避難率、意識というのがかなり低い設定になっているかと思うんですけれども、県内の津波からの避難の県民の意識というのは、現状どのように、高まっているのか、高まっていないのか、そのあたりの状況についてはどのように見られてますでしょうか。
(知事)
今ですね、甚大な津波被害が想定される宇和海沿岸の市町を対象にして避難訓練の取り組みを、基本的には市町が主体的にやるんですけれども、県も当然一緒になって後押しをするということで、支援をしております。自主防災組織等の訓練実施率は70パーセントを超える見込みとなってまいりました。その他に避難路への外灯や転落防止柵等の設置も進めておりまして、令和7年度までの計画が、やらないといけないんだなというところが421箇所を想定しているのですが、現在約265箇所、約6割は完了しておりますので、さらにこれを100パーセントを目指して準備を進めていきたいと思います。 避難のデータあるかな。宇和海沿岸の5市町でですね、令和6年度の見込みなんですけども、津波避難訓練の実施率は74パーセントでございます。489団体のうち362団体が実施をされています。ただですね、夜間は訓練ががくっと落ちまして約30パーセント、同じく489団体のうち夜間の避難訓練を実施したところが146ですので、約30パーセント。先ほど申し上げましたように、夜間避難に必要な環境整備は、63パーセントという整備率ということでございます。こうしたような数字をもとに、課題が各市町に出てまいりますので、じゃあこれを上げていくためにはどうしたらいいかという取り組みをまずは市町主体で、県が支援するという形で充実を図っていきたいと思います。
(愛媛新聞社)
愛媛新聞です。よろしくお願いします。
坊っちゃん劇場の関係でお尋ねします。坊っちゃん劇場の運営に関わる2社が助成金を不正受給していたということで愛媛労働局が公表をされました。これまで愛媛県も観劇支援事業などを通じて劇場に関わってきた立場でいらっしゃると思うのですが、一部で税金による支援を受けているような、半ば公的な側面もあるような事業者による不正受給事案というふうに今回言えると思うのですが、その点も含めて本件をどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。
(知事)
はい。本当に残念でなりません。十数年以上の歴史を積み重ねてきた県内でも、これ全国でもここしかない地域に、なんて言うんですかね、常設された年間通じたミュージカルが、しかもプロの質の高いミュージカルが観劇できる。そしてまたそうした役者さんたちが地域にもどんどん足を運んで、文化芸術の裾野拡大の活動もされてきた経緯があります。大変ファンの方も多くですね、本当にそういう中で、運営の問題ですから、そうした素晴らしい観劇を作り上げてきた方々の、一緒くたにはしない方がいいのかなというふうには思っています。
ただ、今回の運営に関しては国、労働局から支給取り消し通告、これを受けましたので、愛媛県でも、この法人に対して国が出した上乗せの交付を行っていますので、県としては、国の対応も踏まえまして、県のこの上乗せの補助金の交付要綱や規則に基づいて厳正に対処をいたします。
すなわち、速やかに国の支給取り消しに対する県助成金の支給決定を取り消して、返還を求めることといたします。
なお、当該2法人からは、国の通告を厳粛に受け止めて、今後県の返還の求めに対しても真摯に対応したいという回答はいただいております。
先ほど申し上げましたように、国内唯一の地域拠点型常設劇場という価値、そして県内の小・中学生、特に子供たち、学校の現場もですね、文化芸術に触れる情操教育にも結び付くということで、ぜひ体験させたいという声も多くあって、ただ、場所が東温市ですから行けない、遠くて行けないっていうとこの、行きたいという声に応えた交通費助成等を中心にバックアップをしているところでございます。本当にそうした背景がある、そして素晴らしい実績も積み上げてきているということを受けて、しっかりとこの問題に対応して、対処をしていただきたいというふうに思っています。
(愛媛新聞社)
そうすると、観劇支援事業に関して3年間の計画で続けてこられていると思うんですけど、今のご回答だとそこは今後も続けていかれるということになるのか、それともそれに関して何か事業者側に県として指導することだったりとか、伝えることはあるのでしょうか。
(知事)
先ほど申し上げましたように、経営とそれからコンテンツ作りに関わっている方々ってのは分けて考える必要があると思っていますので、今回の問題は経営側の問題ですからそこはしっかりと対応していただきたいというふうに思います。
(愛媛新聞社)
それを伝えた上で観劇支援事業を続けていかれるお考えだと。
(知事)
そうですね。
(愛媛新聞社)
はい、ありがとうございます。
それと上乗せの県の分の助成金の取り消し自体は、これはまだしていなくて今後されるというのか、そのスケジュール感はいかがでしょうか。
(知事)
これはもうできるだけ早くやりたいと思います。
(愛媛新聞社)
ありがとうございます。これ最後なんですけども、今回不正受給と判断された2社と同じ代表者の方の会社が、県の施設の指定管理をしている状態かと思うんですけども、この点に関しては今後どのように取り扱っていかれるのか、いかがでしょうか。
(知事)
そうですね、今回の対応を見た上での判断ということになるのではないでしょうか。
(愛媛新聞社)
不正受給をしていたという事実をもってたちまちどうする、こうするということではなく。
(知事)
ということではないですね。悪質性とかそういうのはすごく判断が難しいところがあって、国の場合はもうルールに従っていなかったら全てどんな内容でも不正受給という形になりますので、そこはきっちりと対応すべきというふうに思っています。
(愛媛新聞社)
国の調査はもう結果が出ておりますけれども、改めて県としてもしっかりと事業者さんに状況確認するだとか、悪質性の有無なんかについてヒアリング等を行っていかれるということになるのでしょうか。
(知事)
いや、それはないですね。今回のことについて言えばもう上乗せは駄目だということを明確に突きつけるということになろうかと思います。
(愛媛新聞社)
指定管理についてはしっかり対応していただくという前提のもとで、続けていかれるという認識なんですか。
(知事)
そこの指定管理の運営に何か問題があった場合は、当然のことながら見直しということになろうかと思います。
(愛媛新聞社)
愛媛新聞です。関連してなんですけど、その指定管理をしている会社についても、労働局の指摘は受けてないんですけども、内部調査を実施しているということでした。雇調金の申請をしているということで、問題がなかったかというのを内部調査しているということでしたけれども、そのあたりも報告は求めていくのでしょうか。県に対してですね。
(知事)
当然そういうことでいいです。
(愛媛新聞社)
その場合もしちょっと問題があった場合っていうのは、ちょっと指定管理についてもどうするかというのは検討の余地があるということは。
(知事)
分かりません、その中身についてはまだ。
(南海放送)
すみません、南海放送です。出生数についてお伺いします。速報値で去年1年間の県内の出生数が7005人となったんですけれども、県では来年2026年の出生数を8500人とする目標を掲げていらっしゃると思います。知事がこの1500人の差の受け止めと、この2年間でどういった施策を通じてこの差を埋めていかれると考えていらっしゃいますか。
(知事)
そうですね、この出生数、もともと県の目標数値は、前もここで申し上げましたように、必ず達成できる目標は意味がないと。頑張ればひょっとしたら達成できるかもしれないところに置こうという前提で各指標を作っています。足らなかった場合は、なぜできなかったのかを分析すれば次につながるという考え方なので、当初から達成できない場合も多分にありますということは申し上げてきたところでございます。その中でとりわけ難しいのが、個人個人の価値観や生き方に関連する出生数、強制できるものは何もありませんから、それを達成していくのが一番困難な分野だと思っています。ただ、どうすれば少しでも上がっていくのかということに関して言えば、もう考えつくことはありとあらゆることをやることに尽きると思ってますから、そういう意味では子育ての支援、あるいはひめボス認証制度等をはじめとする職場環境、これは民間が最終的には決めることですけれども、そのインセンティブになるような施策の展開、そして一番多かった、(結婚)したいけれども、知り合うきっかけがないことでの出会いの創出、もうこうしたことも組み合わせて地道にやり続けることに尽きると思っています。
(日本経済新聞社)
すいません。日経です。3日後の日曜日に大阪万博が開幕しますけれども、改めて愛媛県としての期待のようなものがあれば教えいただけますか。
(知事)
そうですね。ちょっといろいろな課題もあるようなので、ニュースで見た上空写真ですけども、本当に各館の工事が間に合えばいいなというふうなことが一点と、それからテストケースで数万人の規模でやりましたけども、事前に課題も抽出できましたので、本番を迎える前に、今回、浮き彫りになった課題をしっかりと対応できたらいいのではないかなと思っています。
ちょっとチケットの状況とか厳しいと聞いていますけども、これだけの大きな国家的イベント、しかも世界が参加するイベントなので、是が非でも成功裏に導いていただきたいと思いますし、大勢の方が来るというインバウンド需要が今日本に向かっていることもあるので、そういうふうなことで全地域、愛媛だけではないですけども、日本全体の情報発信をする良い機会を持てるのではないかなと期待をしています。
そういう中で、愛媛県独自の万博会場での取り組みや、それから各市町も新居浜市であるとか、南予の9市町が連携して万博で情報発信する取り組み、四国中央市も書道パフォーマンス等々を行う予定で、新居浜、四国中央市、南予9市町がPRを行うこととしておりますので、しっかりと対応をしていきたいと思います。
そして、先般、三井住友海上火災保険から入場チケットをご寄附いただきましたので、「ひめボス宣言事業所」に配付をしたいと思っております。ぜひ、県内からも行っていただけたらと思います。特に大屋根のリングには本県産のCLTが約8割使用されておりますので、ぜひご覧いただけたらいいのではないかなと思います。
ただ、非常に難しいのは愛媛県の場合ですね、大阪からのアクセスが条件的には厳しい。近くにある都道府県とは違いますから、その中でどれだけこっちに足を向けていただけるかは、アクセスの条件からすると非常に難しいとは思いますけども、精一杯のことはやってみたいと思っています。
(読売新聞社(幹事社))
その他ありませんでしょうか。
(愛媛新聞社)
すみません。愛媛新聞です。年度末に発生した今治の山林火災についてなんですけれど、平成以降では過去最大の規模というふうにお伺いしておりまして、鎮火の判断はされていないと思うんですけれども、県内の他の場所でも再発の可能性があるのかなというところで、今後の検証とか、これからの備えというところ、どのように考えられていらっしゃいますでしょうか。
(知事)
まだ鎮圧の段階で残火処理の段階ですから、これはもう現場の今治市、西条市の最終判断というところになりますけれども、なんとか落ち着いているという状況にあろうかと思います。そういう中で、山林火災、火災が起こった場合は、これは消防行政というのは、市町が担いますので、その判断に基づいて県に要請があって動くということなので、県の立場から言えば広域への呼び掛けや国への働き掛けを現場から要請があったら速やかにやると、ですから、来るという前提で事前準備もしっかりしたうえで、来たら速やかに動くことに力を尽くすということが、大事な使命だと感じております。その観点で今回を振り返ってみますと、3月23日に発生しました。今治市、西条市で対応をしました。その日の夜の19時半ぐらいに県の方に自衛隊の大型ヘリの消火が必要になるということになりましたので、災害対策本部を21時30分に開催しまして、そのまま自衛隊に要請をつなぎさせていただきました。翌朝には、もうすでに、徳島のほうからは最初から早く防災ヘリを出してもらっていたんですけれども、自衛隊ヘリも翌朝から対応が始まったということで、最短でできたのではなかろうかと思います。そしてその後もですね、もう一つあったのが、県内の消防関係の呼び掛け、これも要請と同時に速やかに対応を行うことができたのではなかろうかと思います。そして最後に飛び火して、緊急消防援助隊の必要性、要請があがってきましたので、これは、結構事前に連絡を取り合っていましたので、速やかに消防庁長官に要請をしましたところ、17時ぐらいに要請したんですけれども、事前に準備していただいていましたので、その足で現場に行ったんですけれども、21時半には広島から到着をして既に作戦会議が行われておりましたので、最短の対応で国からも派遣をいただいたのではなかろうかと思います。こうした事前準備、そして速やかな活動開始ということが非常に大事だなということを改めて思いました。もう一つはですね、人命の犠牲者がいなかったことが、不幸中の幸いで、これは今治市長、西条市長にも無駄足になっても広範囲に呼びかけた方がいいのではないかということを申し上げたのですが、しっかりと対応されて、その呼び掛けを住民の皆さんが受け止めて冷静に動いていただいたことによって人命被害がなかったということにつながったのではなかろうかと思います。心から感謝を申しあげたいと思います。
もう一つは、あくまでも僕の感覚ですが、規制はできないですね、野焼き等々は、例えばですね、雨の降らない日が続く、乾燥している季節、さらに気象庁の予報で強風が吹き荒れる可能性あり、という三つの条件が今回大きな火災につながっていますから、ある程度の指標でそのレベルを超えたら注意喚起を大々的に行う県のルールみたいなものを作ってもいいかなというふうに思っていますので、何ができるかこの場ではわかりませんけれども、原課に検討を指示しております。
(読売新聞社(幹事社))
その他ございませんでしょうか。それではこれで会見を終わります。
※定例記者会見一般質問で質問のあった米政権が打ち出した関税政策への対応等につきましては、記者発表要旨に記載しています。
※議事録については、読みやすさや分かりやすさを考慮し、発言の趣旨等を損なわない程度に整理しております。