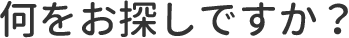本文
薬の基礎知識
薬の正しい使い方
1 添付文書(能書)などを必ず読みましょう。
添付文書(能書)などには、用法・用量、効能・効果などのほか、使用上の注意、副作用が記載してあります。
必ずよく読んでから使用する習慣を身につけましょう。
2 用法・用量を守りましょう。
薬の作用は、使用量と深い関係にあります。ある量以下では作用が現れないし、ある量以上では有害な作用を生ずるおそれがあります。
定められたとおりの用法・用量を守りましょう。
3 服用時間を守りましょう。
薬は、それぞれ定められた時間に飲まないと効果がなかったり、副作用を生じることがあります。
薬の服用についての指示のうち、食前、食後、食間とは次のことをいいます。
食前:
胃の中に食べ物が入っていないとき。(食前1時間から30分)
食後:
胃の中に食べ物が入っているとき。(食後30分以内)
食間:
食事と食事の間のことで、たとえば朝食と昼食の間。食事中に服用するということではありません。
定められたとおりの服用時間を守りましょう。
4 服用時の注意を守りましょう。
副作用の発生を防いだり、薬の効果を正しく発揮させるために多種多様の剤形があります。錠剤、カプセル剤などを服用するときは、次のような注意を守りましょう。
錠剤・カプセル剤:
胃では溶けず、腸ではじめて溶けて効くようにつくられたものがあります。むやみに噛んだりつぶしたりしてはいけません。乳幼児には原則として使用してはいけません。
液剤:
主成分が沈んでいたりしますので、よく振ってから飲みましょう。薬を汚染する原因となりますので、瓶に直接口をつけたり、飲むときに使ったスプーンを薬の入った容器に入れてはいけません。また、目薬の容器の口を直接目につけてはいけません。
5 薬の併用をさけましょう。
薬を併用すると、お互いの作用が弱くなったり、強くなったりして期待する効果が得られないことがあります。また、思わぬ副作用が現れたり、正確な診断の妨げになることがあります。特に医師の指示で薬を使用しているときには、医師の了解を得ないで他の薬を使用してはいけません。
6 高齢者の薬の使用は特に注意しましょう。
高齢者は、血圧の薬や心臓の薬など、多くの薬を併用することが多くなり、使用期間も長くなりがちです。また、肝臓、腎臓などの働きが弱くなっているため、薬の作用が強く出過ぎたり、思わぬ副作用が出ることがありますので、医師・薬剤師などの専門家から十分服薬指導を受けて、正しく使いましょう。
薬の正しい保管のしかた
1 乳幼児・小児の手の届かない所に保管しましょう。
乳幼児・小児の誤飲事故を防ぐため、手の届かないところで保管しましょう。また、薬を飲んだら放置しないで、すぐに保管場所に戻しましょう。
2 湿気、日光、高温をさけて保管しましょう。
薬は、湿気、光、熱に弱いので、フタを固くし、直接日光の当たらない場所に保管しましょう。
液剤や点眼剤、座薬はビニール袋などに包んで冷蔵庫に入れておきましょう。
3 薬以外のものと区別して保管しましょう。
誤用を避けるために、飲み薬とぬり薬は区別して保管しましょう。また、農薬、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管してはいけません。
4 他の容器への入れかえはやめましょう。
薬を使い古しの他の容器に入れかえることは、内容や使い方がわからなくなり、誤用や事故のもとになります。
5 古い薬の使用はやめましょう。
薬には有効期間が表示されているものがあります。
期間を過ぎたものは捨てましょう。また、古い薬や外観に異常があるような薬については、使用前に医師・薬剤師に相談しましょう。
もし薬を使って体調等に異変を感じたら・・・
薬を使っているときに異変を感じたら、まずはお医者さんまたは、お近くの薬剤師にご相談ください。
薬による副作用がもし起こってしまった場合~医薬品副作用被害救済制度について~
薬は正しく使っていても、副作用が起こる可能性もあります。万一、入院治療が必要になるほどの健康被害がおこったとき、医療費や年金などの給付を行う制度があります。「医薬品副作用被害救済制度」は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に基づく公的制度です。
医薬品副作用救済制度について<外部リンク>
制度の概要について<外部リンク>
<救済制度に関する相談窓口>
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部企画管理課
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:(月曜日~金曜日)9時~17時(祝日・年末年始を除く)
Eメール:kyufu@pmda.go.jp
<資料請求・本制度の出前講座についてのお問い合わせ窓口>
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部企画管理課
電話番号:03-3506-9460
Eメール:kyufu@pmda.go.jp
出前講座について<外部リンク>